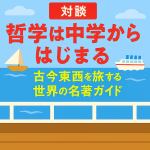議員の社会保険料をごまかす手口
政権与党の一部に、所属議員たちが〝かぎりなくグレーな手法〟で健康保険料逃れをしていた疑惑が浮上している。
「身を切る改革」を声高に訴え、「社会保険料を下げる改革」を掲げている日本維新の会。その維新の地方議員のなかに、「一般社団法人の理事」に就くことで社会保険料の負担を低く抑えている者が複数いることが判明した。
しかも、この手口を宣伝して勧誘している悪質な「一般社団法人」の代表理事も、維新関係者だというのだ。
この問題が大きく注目を浴びたきっかけは、12月10日の大阪府議会定例会。占部走馬府議(自民党)の一般質問だった。
占部府議は、「フリーランス 社会保険」で検索すると出てくるというネット広告を議場のモニターに提示したうえで、次のように問うた。
通常、個人事業主や企業に属さない方は国民健康保険に加入していますが、この広告にあるように、一定の所得以上の方が最低額の社会保険に加入して、その費用を抑える手口があるようです。
その手法は、一般社団法人の理事に少額報酬を支払い社会保険加入資格を得させる、実質的な制度の悪用であります。
保険料を下げたい、厚生年金に入りたいフリーランスを集め、法人が理事報酬や取り分、法人負担分の保険料を「協力金」などの名目で徴収し、その資金で最低額の社会保険に加入させるという仕組みです。
実働はアンケート回答程度で、本来の趣旨をはずれた脱法的運用と指摘をされております。(占部府議の一般質問「大阪府議会定例会」12月10日)