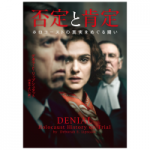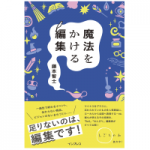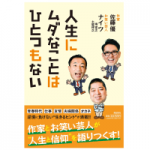法廷闘争のリアルな記録
本書(『否定と肯定』)を原作とした同名の映画が、日本でも2017年12月から封切られた。その公開に合わせて同年11月に刊行された邦訳だ。
ナチスによるホロコースト(大量虐殺)があったことを、はたして司法の場で証明できるか。本書は、実際にイギリスでおこなわれた1779日におよぶ法廷闘争のノンフィクションである。
著者であるデボラ・E・リップシュタットはユダヤ人女性。父親はドイツが第三帝国となる前にアメリカに亡命し、母はカナダ生まれ。
彼女は、ニューヨークのマンハッタンで育った。現在はジョージア州にあるエモリー大学で、現代ユダヤ史とホロコースト学を教える教授だ。 続きを読む