「まず謝れよ国民に」
2019年7月の参議院選挙で、野党が〝争点〟だとしたのが「消費税」と並んで「年金不安」だった。
金融審議会「市場ワーキング・グループ」が提出した報告書に、
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職の世帯では毎月の不足額の平均は約5万円であり、まだ20~30年の人生があるとすれば、不足額の総額は単純計算で1300万円~2000万円になる。
と記載されていたことを、立憲民主党や国民民主党、日本共産党など野党がいっせいに問題視したのだ。 続きを読む
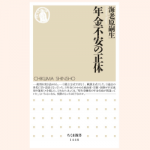
2019年7月の参議院選挙で、野党が〝争点〟だとしたのが「消費税」と並んで「年金不安」だった。
金融審議会「市場ワーキング・グループ」が提出した報告書に、
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職の世帯では毎月の不足額の平均は約5万円であり、まだ20~30年の人生があるとすれば、不足額の総額は単純計算で1300万円~2000万円になる。
と記載されていたことを、立憲民主党や国民民主党、日本共産党など野党がいっせいに問題視したのだ。 続きを読む
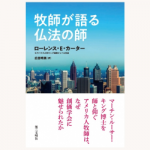
本書『牧師が語る仏法の師』は2つの意味で、読者にとって有益なものをもたらすだろう。
第1は、マーチン・ルーサー・キング・ジュニアが真にめざしていたものは何だったのかということへの、洞察と理解である。
第2は、創価学会の世界宗教化とは、どのようなプロセスと展開を経ていくのかということへの想像力である。
本書の原題は『A Baptist Preacher’s Buddhist Teacher』(バプティスト牧師の仏法の師匠)。
2018年11月に米国のミドルウェイ・プレスから出版された同書は、キリスト教のもっともすぐれた書籍を選出するイルミネーション・アワードの「回想録」部門で、2019年の金賞に輝いた(「聖教ニュース」2019年4月22日より)。
著者のローレンス・E・カーターは、キリスト教バプティスト派の牧師であり、マーチン・ルーサー・キング・ジュニアの母校モアハウス大学にある「キング国際チャペル」の所長である。 続きを読む

SGI(創価学会インタナショナル)が結成されたのは、1975年1月26日のことである。
結成の地となったのは太平洋に浮かぶグアム島。51ヵ国の代表が集っての第1回世界平和会議においてであった。
グアム島は太平洋戦争の激戦地でもあり、米兵およそ1400人、日本兵およそ2万人が命を落としている。その小さな島から、池田大作・創価学会第3代会長(当時)は世界平和への新たな「民衆による潮流」を起こそうとしていた。
代表たちが名前と国籍を記した記念の署名簿。池田会長は、自らの国籍欄に「世界」と記した。 続きを読む

本日、我々が発表する17の持続可能な開発目標と169の関連づけられたターゲットは、統合され不可分のものである。このような広範でユニバーサルな政策目標について、世界の指導者が共通の行動と努力を表明したことは未だかつてなかった。持続可能な開発に向けた道を進むにあたって、すべての国や地域に進展をもたらすウィン・ウィンの協力と地球規模の開発のために我々が一つとなって身を費やすことを決めた。
これは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の一節である。
ちなみに、この2015年11月30日からは、COP21(第21回気候変動枠組条約締結国会議)がフランスで開催され、「京都議定書」(1997年)に代わる新たな気候変動に関する国際協定として「パリ協定」が採択された。
前回述べたように、この国連サミットにおいて2016年から2030年までの国際目標として掲げられたのがSDGsである。 続きを読む

SDGs(Sustainable Development Goals)は「持続可能な開発目標」と訳される。
「持続可能な開発」とは、「将来の世代の欲求を満たしつつ現在の世代の欲求も満足させるような開発」のことだ。
つまり、資源の有限性や環境破壊を無視して、現在の世代の欲求だけが満たされればよいという利己的な繁栄をめざすのではなく、子や孫、その先の子孫といった将来の世代に対しても公平な社会のあり方をめざす概念である。
この「持続可能な開発」という概念が国際社会から注目されるようになったきっかけは、1987年に「環境と開発に関する世界委員会」(ブルントラント委員会)が出した報告書『我ら共有の未来』だった。 続きを読む