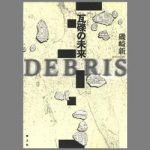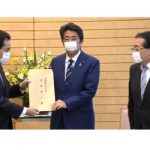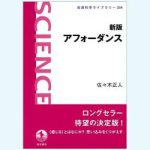子供のころ、いくつか憧れた仕事があった。まず、船乗りと建築家だ。広い海に出て世界をめぐるのは、何とも愉快な仕事におもえた。それから自分の好きなように道路を引き、橋を架け、ビルを建てるのも、同じように愉快におもえた。
ところが、僕にはできないと分かった。僕には、色弱という生まれつきの眼の異常がある。赤や黄色やはっきりとした色の見分けはつくのだが、微妙な色の違いがわからないのだ。
船乗りは通信に手旗信号を使う。その色の見分けがつかないといけない。建築家は電気の配線などを指示する。やはり、その色の見分けがつかないといけない。僕にはそれができないのである。
このことを知ったとき、子供なりにショックだった。母親に不満を述べた。そうしたら、彼女は、ふん、と鼻先で笑って、産んでもらっただけありがたいとおもえ、とうそぶいた。僕は驚いて言葉を失った。 続きを読む