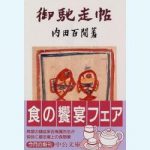「負けに不思議の負けなし」
統一地方選挙・衆参補欠選挙が終わった。補欠選挙では自民党が擁立して公明党が推薦する候補が4勝1敗。ただ千葉5区と参院大分選挙区は僅差の接戦であり、維新が制した和歌山1区も含めて与党側に多くの課題が残った。
一方、立憲民主党は補選で完敗し、執行部の責任を問う声があがりそうだ。日本共産党は議席の4分の1を失った前半戦での大敗に続き、後半戦でも91議席を減らす〝ひとり負け〟となった。
公明党は後半の市議選で891人が当選し、市議の会派別議員数では引き続き最多となったが今回は2議席を落とした。また、東京の特別区議選でも8人がはじき出され完勝を逃した。
大勢が判明した24日の朝、ツイッターのタイムラインにこんな言葉が何度も流れてきた。 続きを読む