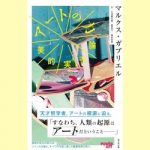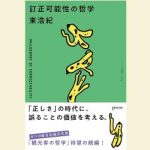世界宗教化と日蓮本仏論
創学研究所(松岡幹夫所長)から『創学研究Ⅱ――日蓮大聖人論』(第三文明社)が刊行された。
創学とは「創価信仰学」のこと。創学研究所は、創価学会の信仰に基づいた学問的な研究をめざし松岡所長が個人として設立した。言うなれば創価信仰学とは創価学会にかかわる「神学」であり、その意味では学問としての仏教学や宗教学とはアプローチがまったく異なる。概略は『創学研究Ⅰ』(2022年刊)の書評(「書評『創学研究Ⅰ』)を参照していただければ幸いである。
松岡所長は今回の『創学研究Ⅱ』の「発刊の辞」のなかで、創価学会の信仰には三つの柱があると思うとし、御書根本、日蓮大聖人直結、御本尊根本を挙げている。
そして、『創学研究Ⅰ』では一つ目の御書根本の視点から現代の仏教学や宗教学の見解、近代以降の日蓮研究の成果を論じたのに対し、今回の『創学研究Ⅱ』は日蓮大聖人直結の信仰に立って、現代の学問的な日蓮論をどう解釈すべきかを論じたと綴っている。
創価学会は、会の最高法規である「会憲」のなかで「教義」として、
この会は、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、根本の法である南無妙法蓮華経を具現された三大秘法を信じ、御本尊に自行化他にわたる題目を唱え、御書根本に、各人が人間革命を成就し、日蓮大聖人の御遺命である世界広宣流布を実現することを大願とする。(「創価学会会憲」第1章 第2条)
と明記している。
今や創価学会は世界192カ国・地域に広がり、世界宗教化の段階に入った。遠からず日本の会員数よりも諸外国の会員数のほうが多くなる時代も視野に入れ、この「日蓮本仏論」をどのように捉え表現していくべきなのかという議論は不可避であろう。
もとより、教団の「教学」としての内実は教団内部で議論し決定することではあるが、創学研究所のような教団外部の存在が受け皿となって、一級の知性たちと闊達な議論を交わしていくことはきわめて有益であり健全なことだと思う。 続きを読む