僕は中学生のころにレイモン・ラディゲを読んでいた。彼は夭折した天才作家なのだが、学校は嫌いだったようで、授業を抜け出し、湖に浮かべた小舟に寝そべって本を読むのが日課だったらしい。
このくだりを読んだとき、羨ましいとおもった。僕も学校は嫌いだったし、本を読むのは好きだった。でも、近所に手頃な湖はなく、まして寝そべることのできる小舟などなかったので、学校の保健室のベッドで本を読んだ。 続きを読む
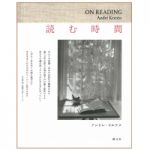
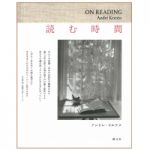
僕は中学生のころにレイモン・ラディゲを読んでいた。彼は夭折した天才作家なのだが、学校は嫌いだったようで、授業を抜け出し、湖に浮かべた小舟に寝そべって本を読むのが日課だったらしい。
このくだりを読んだとき、羨ましいとおもった。僕も学校は嫌いだったし、本を読むのは好きだった。でも、近所に手頃な湖はなく、まして寝そべることのできる小舟などなかったので、学校の保健室のベッドで本を読んだ。 続きを読む
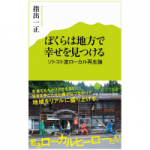
環境をテーマにした『ソトコト』という雑誌があることは知っていた。でも、読んだことはなかった。最近になって、「ソーシャルデザイン」について調べ始めて、この雑誌が〝ソーシャル〟(社会や地域、環境をよりよくしていこうとする行動やしくみ)もテーマにしていると分かって、ときどき買うようになった。
現在の編集長・指出(さしで)一正によれば、3・11の震災以降、それまでの雑誌の方針を転換し、環境に加えて〝ソーシャル〟を掲げたのだという。いい感度をしているとおもう。指出が注目しているもう一つのテーマは、〝ローカル〟である。 続きを読む
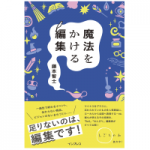
このところ、なんだかローカル=地方がおもしろいことになっているようだ。かつては、クリエイティブな若者たちは東京をめざしたものだが、いまやそうではない。あちこちの地方に根差して仕事をする人々が増えているのだ。
そのプレーヤーの1人が藤本智士(さとし)である。若いといっても40代なかば。この分野の先駆者といえる。兵庫県西宮市に住んで、編集者として活動している。『魔法をかける編集』は、彼の仕事振りをトレースした本だ。
2006年に『Re:S(りす)』という雑誌を立ち上げた。これはRe:Standard=「あたらしい〝ふつう〟を提案する」というのがコンセプト。全国誌だけれど、編集部は大阪にあった。「東京では売れない雑誌」をめざして、全国の〝田舎〟に向けて発信する。
このあたりから、すでにおもしろそうではないか。 続きを読む
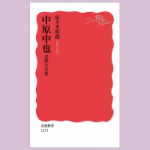
作家になる、と宣言して高校を中退した。若気の至りである。もちろんすぐに作家デビューできるわけもなく、高校中退の身の上では、ろくな働き口もなく、さまざまなアルバイトを転々とした。
なかでもきつかったのは、建設現場の力仕事だった。穴を掘ったり、セメントをこねたり、資材を運んだり。昼前には、くたくたになる。ただ、若かったから食欲はあって、昼の弁当は、このうえなくうまかった、
朝の早い仕事だから、終わるのも早い。日没前には帰り支度をする。しかし僕は、まっすぐ家へ帰らない。途中で喫茶店に寄るのだ。 続きを読む
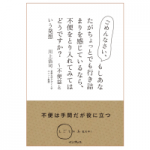
人が便利さを求めるようになったのは、いつごろからだろう。考古学が教えるところでは、まず、人は石器を手にし、ついで青銅器を持ち、やがて鉄器を使うようになった。これは、より便利な道具を求めるようになったと考えられる。
しかしもっと遡ると、人が両手を自由に使うようになったのは、やはり、便利さを求めてのことだったろうから、人類は発生してから間もなく、本能的に便利さを追い求めてきたといってもいいのではないか。
すると、「不便益」というアイデアは、実は、かなり壮大な転換の兆しなのかもしれない。 続きを読む