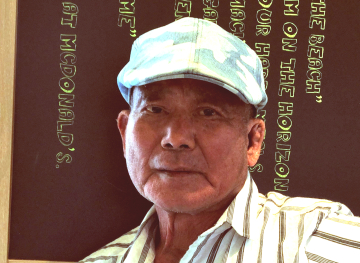戦後の日本本土で隆盛を極めたフルコンタクト空手の元祖・極真空手。実際にその歴史をたどれば、沖縄発祥の空手から枝分かれした一部にほかならない。その極真空手に人生の若いころに命を賭け、その後、源流である沖縄空手に価値を見出した空手家を何人か取り上げてきた(「極真から沖縄空手に魅せられた人びと」《第26回、第27回、第28回》参照)。この連載の最後にインタビューを行った剛毅會(ごうきかい)空手道の岩﨑達也宗師(いわさき・たつや 1969-)もその一人だ。取材の最初にクギを刺されたのは、「武術性があるかどうかが問題であって、自分にとってそれが沖縄空手でなければならないということではない。たまたま師事した(沖縄空手の)先生がものすごい武術性を持っていた」という言葉だった。沖縄空手の本質とは何なのか、インタビューを試みた。 続きを読む