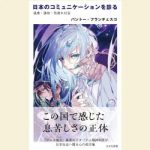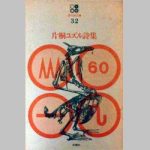心の痛みを伝えることが苦手な日本人
著者はイタリア出身の33才の精神科医である。18才まで故郷のシチリア島で過ごし、ローマの大学で学び医師となる。その後、幼い頃より主にアニメを通して憧れを持っていた日本に留学し、医師免許と医学博士号を取得した。史上初めて日本とイタリア両国で医師国家試験に合格した稀にみる秀才である。日本の文化に造詣が深いだけでなく、見事に日本語を使いこなす。それは本書の冒頭を読むだけでも分かるだろう。現在はその能力を活かし、医療現場だけでなくコメンテーターや著述家としても活躍の場を広げている。
本書はコロナ禍の日本で医師として過ごした経験をもとに執筆された。その間、自身が感じた疑問や違和感を精神科医の観点から深く掘り下げ、現代の日本社会の問題にメスを入れる。医学者としての〝冷静な視点と〟日本人を深く愛する〝暖かな眼差しが〟が両立している。ここに本書の大きな魅力の1つがある。
肥大化した自己を引きずったまま、負の感情の扱い方や伝え方がわからないという、外傷コミュニカビリティの未熟な人が大勢いる。彼/彼女らは心の痛みを自覚できず、他者に助けを求めることができない。一方、健全なトラウマを体験してきた人は外傷コミュニカビリティを備えており、他者に「自分はこういう風に苦しい」と伝えられる。(本書26ページ)