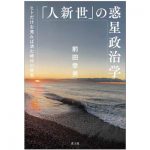「池田思想」としての『法華経の智慧』
作家の佐藤優氏によって月刊誌『第三文明』2016年8月号から開始された連載「希望の源泉 池田思想――『法華経の智慧』を読む」が遂に完結し(2025年6月号)、その単行本化の最終巻となる第8巻(『希望の源泉 池田思想⑧』)が刊行された。
まず『法華経の智慧』は、SGI(創価学会インタナショナル)会長でもある池田大作・創価学会第3代会長(以下、原則としてSGI会長と表記)が、1995年初頭から1999年6月までの期間に、法華経28品の全編を創価学会教学部の代表との座談形式で講義した書物である。
法華経は大乗経典の代表的な経典として、その成立から約2000年間にわたって多くの地域で多くの言語に翻訳された。ゆえに「経の王」とも称されている。
とりわけ鳩摩羅什訳の「妙法蓮華経」は、日本を含む東アジアの仏教体系、政治、文化にも多大な影響を与えてきた。創価学会が信奉する日蓮大聖人も、鳩摩羅什訳の「妙法蓮華経」を用いている。 続きを読む