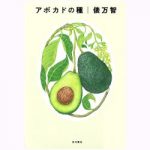「2位」にも遠く及ばない惨敗
東京都知事選挙が終わった。2期目の任期満了を迎えようとしていた現職の小池百合子知事に対し、立憲民主党の参議院議員だった蓮舫氏が立候補を表明。過去30年ほど知名度のある候補者の当選が続いてきただけに、当初はメディアも事実上、蓮舫氏と小池氏の対決になるのではと見ていた。
ところが投票箱が開いてみると、3期目に挑んだ小池氏が291万8015票で午後8時〝ゼロ打ち〟の圧勝。広島県安芸高田市長だった石丸伸二氏が165万8362票で2位。蓮舫氏は石丸氏の4分の3にしか届かない128万3262票で、小池氏にはダブルスコア以上の大差をつけられ惨敗した。
東京生まれの東京育ちで20年間も東京を選挙地盤にしてきた蓮舫氏が、接戦に持ち込むことさえ遠く及ばず、なぜこんな結果に終わったのか。朝日新聞は「何が原因かよくわからない」という選対幹部の言葉を報じた。だが、蓋が開くまで大敗を予測できていなかったその〝認知のゆがみ〟こそが、大惨敗の原因のすべてではなかったか。 続きを読む