第110回 正修止観章 70
[3]「2. 広く解す」68
(11)病患境②
(2)別釈①
別釈は、「病を観ずるに五と為す。一に病の相を明かし、二に病の起こる因縁、三に治法を明かし、四に損益(そんやく)、五に止観を明かす」(第三文明選書『摩訶止観』(Ⅲ)、近刊、頁未定。大正46、106b13~14)とあるように、五段に分かれる。順に紹介する。 続きを読む

(2)別釈①
別釈は、「病を観ずるに五と為す。一に病の相を明かし、二に病の起こる因縁、三に治法を明かし、四に損益(そんやく)、五に止観を明かす」(第三文明選書『摩訶止観』(Ⅲ)、近刊、頁未定。大正46、106b13~14)とあるように、五段に分かれる。順に紹介する。 続きを読む

――2026年も年頭から国内外の政治に目まぐるしい動きが続いています。まず1月3日(現地時間)未明、トランプ大統領の命令を受けた米軍が、南米ベネズエラの首都カラカスを含む複数の拠点を爆撃。同時に特殊部隊(デルタフォース)による急襲作戦を実行して、ニコラス・マドゥロ大統領夫妻を拘束して米国内へ移送しました。
青山樹人 「自由」と「民主主義」「法の支配」「基本的人権」などを価値観としていたのが米国です。その米国が他の主権国家に武力攻撃を加えて国家元首を拘束連行しました。
議会の承認さえ得ていなかったことについて、トランプ大統領は合衆国憲法第2条に基づく権限(最高司令官としての権限)だと主張していますが、議会からは民主党を中心に「宣戦布告の権限を持つ議会を軽視しており、違憲である」との批判が噴出しています。
いずれにしても、これではロシアによるウクライナ侵攻をはじめ、大国が〝力による現状変更〟を試みようとすることに正当性を与えてしまうと懸念されています。 続きを読む
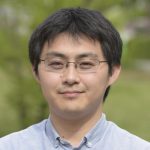
2月8日投開票となる総選挙がいよいよ始まりました。
2月1日発売『第三文明』3月号からNPO法人ほっとプラス理事・藤田孝典氏の記事を先行配信します。 続きを読む

解散から投票まで16日という〝戦後最短〟の衆議院選挙が公示となった。
首相が自民党首脳にさえ伝えずに電撃解散に打って出たことで、図らずも野党側でも中道改革連合という新党が結党された。
与党側は「政権の枠組みが変わったのだから、その信任を問う選挙だ」と主張する。しかし、物価高騰対策が喫緊の課題になっているのに、通常国会も開かず、新年度予算の年度内成立を犠牲にしての解散総選挙は、あまりにも代償が大きい。 続きを読む

高市首相は1月23日、衆議院の解散を決定し、1月27日公示、2月8日投開票となる総選挙がいよいよ始まります。
2月1日発売『第三文明』3月号掲載、九州大学名誉教授・藪野祐三氏による「民主主義を機能させる生活者重視の《中道》思想」を先行配信します。 続きを読む