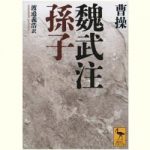時代の転換点を生み出した強烈な才能
中国の歴史小説『三国志』は日本でも多くの愛読者を持つ。登場する英雄のなかでひときわ異彩を放つ人物のひとりが曹操である。小説の曹操は軍事や謀略に長けた乱世の奸雄として描かれる。しかし史実によれば、文学や学術の分野での才能にも長けた多才な人物であった。
曹操は、さまざまに伝えられて来た孫子の兵法を比較し、黄老思想(伝説上の人物黄帝・老子の説いたとされる教え、後に道教に発展する)との関係の深さに着目し、正しい伝承を選び採り、洗練した文章に書き改め、13篇からなる『孫子』の本文を定めた。さらに自から注を付け、完成させたものが本書『魏武注孫子』(ぎぶちゅうそんし)である。
本書はその全訳と解説である。さらに読者の便宜を図るために、訳者が『三国志』から選んだ孫子兵法の応用事例を20収録したものである。
現存する『孫子』は、全てこの版に基づいている。曹操は一級の知識人としても後世に名を残したのである。
(道とは君主が)民たちを教令で導くことをいう。(本書14ページ)
注は簡潔な文で書かれているが、そのなかにも曹操の考えが強く反映している箇所がある。
「始計篇」では、戦争を始めるにあたって自軍と敵軍の戦力を入念に分析する必要性を説き、着目すべき5つのポイントを挙げる。
その1番目は「道」である。多くの注釈家は「道」を「仁(博愛精神)と義(道理にかなった行動)」と道徳的に解釈した。しかし曹操は「道」とは「君主の教令で導く」と、リーダーシップの重要性を説く。訳者はこの注に時代背景と曹操の立場が色濃く反映していると解説している
曹操が活躍した三国時代は、儒教を国家の支配原理とする後漢の崩壊と共に始まる。そうした状況下で曹操は、儒教以外の思想にも目を向け、閉塞した時代を突破しようとする。「健安文学」と呼ばれる中国史上初の文学運動を自らリードし、唯才主義と呼ばれる新しい人材登用の方針を採用した。こうした試みが後に実を結び、仏教や道教といった宗教が盛んになり、文学や書画が発展していく。曹操の強烈な個性と才能が時代の大きな転換点を生み出したのである。
敗北にも学ぶ柔軟な姿勢
軍を興せば(敵地に)深く入り長距離を行軍して、敵の都を占拠し、敵の都と国の内外を遮断して、敵が国をあげて降参し帰属することを上策とする。(本書47ページ)
伝統的に、注は本文の意図を明確にするためのものと考えられていた。本書のほとんどの注もその慣例に従っている。しかし、僅かではあるがこの慣例を破り、本文の意図に反する注を付けた箇所もある。『孫子』本文では戦闘を避け敵国を屈服させるのが上策としている。しかし、曹操の注には、敵の首都を急襲し占領して、内外の連携を断ち、一挙に降伏させるのが上策とある。訳者は、曹操がこうした注を付けたのは赤壁の戦いの経験があったからではないか、と推測する。
〝勝敗は兵家の常〟とよくいわれるが、軍略の天才と称される曹操も幾度も敗北を喫した。特に劉備・孫権連合軍と交戦した赤壁の闘いでは、多くの将兵を失うばかりか、自身も絶体絶命の窮地に陥ってしまう。このとき曹操は〝戦わずして勝つ〟降伏工作に拘り続けた。それが孫権配下の武将・黄蓋の偽装降伏に騙される原因となり、手痛い敗戦を招いてしまった。訳者は、曹操がこの大敗から学び、あえて本文の意図に反した注を付したのでは、と考えている。
転んでもただでは起きないどころか、失敗から貪欲に学び、次なる勝利への教訓を導き出そうとする。このしたたかで柔軟な姿勢が、曹操の強さの秘訣であったのかもしれない。
『孫子』が説く軍略思想の要諦とは?
このため百戦して百勝することは、最善ではない。戦わずに敵の軍を屈服させるのが、最善である。(本書47ページ)
怒りはまた喜ぶことができ、恨みはまた悦ぶことができるが、亡国は再び存在できず、死者は再び生き返らない。そのため明君は戦争を慎重にし、良将は戦争を戒める。(本書228ページ)
『孫子』は「兵は詭道である=戦争とは騙しあいである」と定義し、合理的で総合的な視点から戦争を徹底的に分析した書物である。曹操だけでなくライバル関係にあった劉備や孫権等の人物たちも『孫子』を学び、巧みに応用した。また現代でも通用する内容を数多く含んでいることから、古典として読み継がれている。
では、『孫子』に説かれる軍略思想はどのような時代背景から生まれたのであろうか。その起源は孫武の教えに遡るとされる。彼が活躍したのは曹操が活躍した三国時代(3世紀)よりもさらに古い紀元前6世紀の春秋時代である。この時代もまた戦乱が続いた時代で、経済は疲弊し、民衆は窮乏していた。そのような惨状を常に目にしていた孫武とその弟子たちは、戦争を研究し合理的に遂行することによって、戦争の惨禍を最小化しようと考えた。〝百戦百勝することを次善とし、戦わずして勝つことを勝つことを最善とする〟とする理由もここにある。彼の軍略思想の要諦は、戦争の抑止にこそある。
1800年後の現代の世界では、科学技術の発展に伴い軍事技術は格段に発達した。戦争も総力戦となり、民衆の受ける被害は比較にならないほど増大し、今では核兵器によって人類を滅亡させることすら可能となった。
近年、ウクライナ危機やガザ地区の問題などが起きて以降、外交や政治交渉よりも軍備増強の必要性を声高に訴える人々もいる。
そうした状況であるからこそ、軽挙妄動で戦争を始めることを厳しく戒め、可能な限り戦争以外の方法で問題を解決すべきと説く、『孫子』の重要性が増しているのではないだろうか。
〝亡びた国は再び存在せず、死者は再び生き返らない〟日本のみならず世界の政治家は、この『孫子』の言葉を心に刻んで欲しいと願う。
『魏武注孫子』
(曹操著、渡邉義浩訳/講談社学術文庫/2023年9月7日刊)
関連記事:
「小林芳雄」記事一覧