なぜ夜回りを始めたか
書評子として、自分の「感情」をあからさまに書いてしまうのは、誉められる話ではない。
じつは第三文明社から本書が届いたとき、書名だけで勝手に内容を想像してしまっていた。
ああ、あの「夜回り先生」として知られる水谷修氏が、きっと公明党の政策なり実績なりを肯定的に評価する書籍なんですね、と。
ところが、プロローグからわずかに読み進めるうちに、不覚にも目頭が熱くなってしまった。それはエピローグを読み終わるまで何度も続いた。 続きを読む
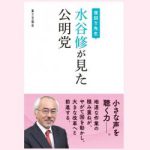
書評子として、自分の「感情」をあからさまに書いてしまうのは、誉められる話ではない。
じつは第三文明社から本書が届いたとき、書名だけで勝手に内容を想像してしまっていた。
ああ、あの「夜回り先生」として知られる水谷修氏が、きっと公明党の政策なり実績なりを肯定的に評価する書籍なんですね、と。
ところが、プロローグからわずかに読み進めるうちに、不覚にも目頭が熱くなってしまった。それはエピローグを読み終わるまで何度も続いた。 続きを読む

この記事は『新版 宗教はだれのものか 三代会長が開いた世界宗教への道』(青山樹人著/鳳書院)の発売にともない「非公開」となりました。
新たに「三代会長が開いた世界宗教への道(全5回)」が「公開」となります。
「三代会長が開いた世界宗教への道」(全5回):
第1回 日蓮仏法の精神を受け継ぐ(4月26日公開)
第2回 嵐のなかで世界への対話を開始(5月2日公開)
第3回 第1次宗門事件の謀略(5月5日公開)
第4回 法主が主導した第2次宗門事件(5月7日公開)
第5回 世界宗教へと飛翔する創価学会(5月9日公開)
WEB第三文明の連載が書籍化!
『新版 宗教はだれのものか 三代会長が開いた世界宗教への道』
青山樹人価格 1,320円/鳳書院/2022年5月2日発売
→Amazon
→セブンnet
第三文明社 公式ページ
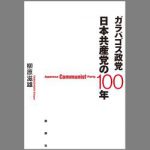
なぜ著者がこの本を書くに至ったのか。
その理由が端的に「エピローグ」のなかに記されていた。
著者は早稲田大学に入学した当時、自分の学部の自治会を仕切っていた「民青」の意味さえよく理解していなかった〝典型的なノンポリ学生〟だったと述懐している。
ちなみに「民青」とは「日本民主青年同盟」の略であり、日本共産党の下部組織である。
卒業後、編集プロダクション勤務などを経て、当時の社会党機関紙『社会新報』の記者になった。
編集部には、政党機関紙『赤旗』が置かれていたが、熱心に読んだ記憶はない。ただし社会党の中でしばしば感じたのは、同党内の強烈な共産党アレルギーで、近親憎悪に似た感情が渦巻いていた。(本書)
1996年末に民主党の結成で社会党は分裂。著者はフリーランスになった。 続きを読む

この記事は『新版 宗教はだれのものか 三代会長が開いた世界宗教への道』(青山樹人著/鳳書院)の発売にともない「非公開」となりました。
新たに「三代会長が開いた世界宗教への道(全5回)」が「公開」となります。
「三代会長が開いた世界宗教への道」(全5回):
第1回 日蓮仏法の精神を受け継ぐ(4月26日公開)
第2回 嵐のなかで世界への対話を開始(5月2日公開)
第3回 第1次宗門事件の謀略(5月5日公開)
第4回 法主が主導した第2次宗門事件(5月7日公開)
第5回 世界宗教へと飛翔する創価学会(5月9日公開)
WEB第三文明の連載が書籍化!
『新版 宗教はだれのものか 三代会長が開いた世界宗教への道』
青山樹人価格 1,320円/鳳書院/2022年5月2日発売
→Amazon
→セブンnet
第三文明社 公式ページ
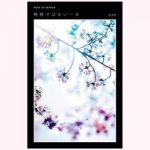
今回の本は、『kaze no tanbun 特別ではない一日』である。キーワードは、「tanbun」だろう。日本語表記にするなら、おそらく「短文」。これを、どのように解釈するかが、まず、ポイントになる。
短い文章――短篇小説、エッセイなど、普通に思い浮かべるのは、そのあたりだろうか。編者は、西崎憲。福岡の出版社・書肆侃侃房(しょしかんかんぼう)から発刊された文芸誌『たべるのがおそい』の編集長を務めた人物だ。
もともと作曲から出発し、翻訳をするようになり、のちに小説や短歌を書くようになった。『たべるのがおそい』が話題になったのは、掲載作から芥川賞の候補作が選ばれたことが大きい。 続きを読む