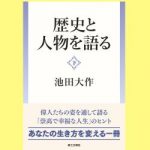「下巻」は仏法者としての人物論
創価学園・創価大学の創立者である池田大作氏は、歴史上の人物論について若き俊英たちに語る機会を幾度か持った。『歴史と人物を語る(上)』には、こうした教育機関での創立者としての講演が収められている。
一方、創価学会の第3代会長を辞した後も、創価学会名誉会長あるいは創価学会インタナショナル会長として、さまざまな機会を通して会員たちにスピーチや随筆などを贈り続けた。
そうした創価学会内での言論でも、池田氏は古今の世界の名著を紐解き、東西の偉人たちの生き方を通して、「真に崇高な生き方とは何か」「幸福な人生とは何か」を語ることが常であった。
多くの場合、宗教指導者の〝説法〟は、その信仰世界の内部の世界観や価値観に閉じたものになりがちだ。池田氏は、むしろそのような独善的なものにならないように、とりわけ青少年世代の会員が普遍的な知性と教養を身につけられるよう心を砕き続けた。
本書『歴史と人物を語る(下)』は、創価学会の学術者会議での講演や聖教新聞紙上に掲載された「随想」などのかたちで、カント、ソクラテス、ナイチンゲール、トルストイ、ベートーベンについて論じた内容を収録している。
目次(リンク)
①「創立の父」とカント(「牧口先生とカントを語る」)
②「わが師の正義を、万人に示すのだ!」(「ソクラテスを語る」)
③「ナイチンゲールに負けてはいけない」(「ナイチンゲールを語る」)
④「破門」によって世界から支持された文豪(「トルストイ」を語る)
⑤苦悩を突き抜けて歓喜に至れ(「ベートーベンを語る」)
「創立の父」とカント(「牧口先生とカントを語る」)
「牧口先生とカントを語る」は、21世紀最初の「創価学会創立記念日」(11月18日)を記念するものとして、2001年11月20日に八王子市の東京牧口記念会館でおこなわれた第一回文化教育学術会議で講演されたもの。
創価教育の父でもある牧口初代会長は、戦時下で「信教の自由」への信念を貫き、戦争遂行のための国の宗教統制に従わなかったことで逮捕・投獄された。
獄中からの最後の葉書は、逝去の約1カ月前の1944年10月13日付。そこには「私も元気デス。カントノ哲学を精読シテ居る」との一文が見える。牧口会長は逝去の直前までカントを読んでいた。
冒頭、池田氏は「熱情なくして偉大なものは成就されたことがない」とのカントの言葉を引く。
創価学会の創立記念日である11月18日は、牧口初代会長が獄中で殉教した日でもある。その牧口会長の名を冠した殿堂で、池田氏は先師が最後まで読んでいたカントを題材に選び、教育者や学術者たちに講演した。
きょうは、先師を偲びつつ、カントの宇宙観、人間観、平和観、宗教観等について、少々、思いつくまま所感を語りたい。もとより、本格的な哲学論ではなく、カントという一個の「真理を求め続けた人間」の誠実さに学びたいという趣旨である。(本書/以下同じ)
カントが最初に関心を持ったのは「自然」であり、とりわけ「宇宙」であった。200年以上前の18世紀に、カントは〝太陽系は星雲状のガス体から生まれた〟という仮説を立てていた。
彼は、大宇宙には多くの星や銀河が存在し、生成、消滅、再生を繰り返していることを見抜いていた。同時に、彼は星のきらめく天空と、わが内なる心の道徳律に、共通するものを見出していた。
池田氏は、それは「宇宙即我」「我即宇宙」と説く仏法にも通ずるものがあると語る。
カントは13歳で母親を、22歳で馬具職人の父親を亡くしている。葬儀の費用にも事欠くほど貧しい暮らしであった。
そんなカントにとって両親から与えられた一番の財産は 〝貧しい中でも教育を受けさせてくれた〟ことであり、〝誠実さを欠いた卑怯な生き方を一度も見せなかった〟ことだと言う。
両親が与えてくれたこの財産は、カントの人生を大きく開き、高みへと成長させてくれた。
庶民として生きる誇り、そして感謝――ここに人類の精神界にそびえ立つカントの出発点がある。
そんなカントは「人間の価値」も追求した。人間の価値は何を得られたかではなく、何を為すのかにある。まさに、仏法に通ずる思想だと、池田氏は言う。
身分や人種、国民ということ以前に、自立した人格を持った存在として人間を見た最初の思想家の1人がカントであったと述べる。
「人類を、自分自身であろうと他人であろうと、いかなる場合であれ、決して単なる手段としてではなく、目的として扱え」
カントが示したこの宣言は、キング牧師をはじめ、その後の世界中の人権運動を鼓舞し続けてきた。
「人間の尊厳」「生命の尊厳」をいかに守り輝かせていくか。これは、池田氏と歴史家トインビー博士が語り合った焦点の一つでもあった。
創価学会は、永遠に、「人間を手段とする」転倒とは断固、戦いぬく。
池田氏はこう力強く宣言する。
この池田氏の講演がなされた2001年11月といえば、米国で「9.11」同時多発テロが起きた直後である。米国は「テロとの戦い」としてアフガニスタンへの軍事侵攻を開始し、講演の1週間前にあたる11月13日には首都カブールを制圧し、タリバン政権を一度は崩壊させていた。
日本でも90年代半ば以降、ナショナリズムが高まっており、池田氏はしばしば「国家主義」への警鐘を鳴らしていた。
池田氏は「人間を手段化する」最たるものとして「戦争」を挙げる。それは、カントの洞察でもあった。
カントは、「人間の権利」を、政治よりも上に位置づけた。
人権を守るために「諸国家の連合体」の構築を主張した。そして「永遠平和」をもたらすことが「最高の政治的善」であると展望したのである。
こうしたカントの「永遠平和論」は、人類初の国際平和機構「国際連盟」の創設を基礎づけたことで知られる。今の「国際連合」にも、つながる。
50年前の1975年、池田氏は創価学会青年部が集めた核兵器廃絶を求める一千万人の署名を、当時の国連事務総長に手渡した。
1980年代に入ると、創価学会インタナショナルが国連広報局のNGOにもなり、〝民衆が支える国連〟という新しいありかたを提起して、一貫した国連支援を続けてきた。
池田氏は、カントの思想と世界観を紹介しながら、同時に創価学会の諸活動がカントの哲学に接続するものであることを示している。
終盤、池田氏の講演は大学のあり方にも言及していく。教育者、学術者の会合であり、参加者には創価大学の教職員をはじめ、多くの大学関係者もいたであろう。
カントが人生の最終章まで母校に尽くしたこと。絶対に手を抜かず、誠実に講義をおこなったこと。その講義は学生にとって「楽しい人間的なふれあいのひととき」であったこと。カントは、学生自らが「思索する力」を身につけることをめざして講義をしたこと。
こうした大学教員としてのカントの姿勢を紹介する一方で、狭い専門に閉じこもり、学問を自分のためのものと考え、〝虚栄の道具〟にしていた当時の多くの学者に対するカントの批判を語る。
それは、学術界に生きる弟子たちに向けた池田氏の厳愛の叱咤でもあり、なかんずく創立した創価大学に奉職する者たちへの遺言にも似た思いであったに違いない。
二〇〇一年十一月十八日、我らは新世紀の幕開けを祝い、「希望の鐘」を乱打し、新たなる大前進を開始した。
尊い、大切な全同志の皆さま方が、絶対に、そして確実に、一人ももれなく「幸福」と「栄光」の人生の勝利者となられんことを心より祈り、私のスピーチとさせていただく。
池田氏の眼には、21世紀のはるか先まで続く、門下の姿が映っていたのではないか。1人も転落させたくない。全員を人生の勝利者にしてあげたい。講演の締めくくりの言葉には、池田氏の大感情がにじみ出ている。
「牧口先生とカントを語る」終わり→目次に戻る
「わが師の正義を、万人に示すのだ!」(「ソクラテスを語る」)
池田氏は翌2002年1月、「聖教新聞」紙上に全6回にわたる新春随想「ソクラテスを語る」を発表した。
ソクラテスとプラトンの師弟について、池田氏はさまざまな折に繰り返し語ってきた。
冒頭、池田氏はソクラテスの有名な言葉「汝自身を知れ」に言及する。
「汝自身を知る」ことは、「人間を知る」ことであり、「他者を理解する」ことに通ずる。そして、それは「人類の共生」「世界の平和」という根本課題へと連動していく。(本書/以下同じ)
「汝自身」の中にこそ、決して尽きることのない、無限の「生命の宝財」が秘められている。
今こそ、人類は、この「汝自身を知れ」という思想の出発点に、真摯に立ち返るべきではないだろうか。
ソクラテスは、わかりやすい言葉で対話する問答法で真理を探究した。真理を与えるのではなく、対話することで、相手の中の真理を目覚めさせていった。
池田氏は、日蓮仏法もまた対話の仏法であり、すべての人の奥底にある仏界の生命を対話によって目覚めさせていくのだと語る。
全6回の随想のなかで、池田氏が語ったソクラテス論は多岐にわたる。そのうえで、あえてここでは3点に絞って紹介したい。
まず1点目は、「青年との対話」である。
ソクラテスは早朝からアテネの広場や街頭に出て、あらゆる人々と開かれた対話を続けた。彼にとって真の哲学とは対話のなかにあった。
その対話の特徴として池田氏は、「わかりやすい言葉」で「わかりやすい事実」を通して、めざすべき「高尚な思想」「神々しい徳」を語ったことだと述べる。
あえてわかりやすい言葉を使って対話を広げるソクラテスを、当時の学者や政治家は嘲笑した。
池田氏はその姿を、日蓮大聖人が庶民の門下のために仮名文字を多用した御書を恥とした五老僧の姿と二重写しに見えると語っている。
当時のアテネにおける教育は、教師が生徒の上に立ち、外側から知識を注ぎ込むような教育だった。
これに対しソクラテスは、青年たちが自らの内側からの力で、自身の知恵を開き、魂を向上させることに取り組んだ。
ソクラテス自身は、それを手助けする「善き友」に徹した。
池田氏が指摘するこのソクラテスの手法は、釈尊が範を示した仏教本来の師弟のあり方にも通じるのではないか。仏法における「師弟」とは、上下の関係ではなく、「善き友」の究極の存在である。
2点目は「政治にかかわる市民の義務」について。
政治について池田氏は、「民衆の幸福な生活を実現し、社会に繁栄をもたらし、世界に平和を築いていくための技術」との恩師・戸田会長の慧眼を紹介する。
ソクラテスもまた政治の真の目的について、〝人間の魂を善なるものへ促していく〟ことと述べている。
これに関連して池田氏は、
「教育」が「政治」に従属するのではない。「政治」が「教育」に奉仕すべきなのである。
と語っている。
じつは2000年頃から日本では「教育基本法」改正の論議が始まり、折からのナショナリズムの高揚も相まって、復古主義的な教育への動きが懸念されていた。
池田氏は当時の教育現場の荒廃や、教育をめぐる政治の不穏な動きを見据え、2000年には「教育提言『教育のための社会』目指して」を、2001年には「教育力の復権へ——内なる『精神性』の輝きを」を発表している。
3点目は、嫉妬社会における冤罪の構図と、「死」という厳粛な審判についてである。
当時のアテネは嫉妬社会であったと池田氏は語る。その風潮を煽ったのが、「ソフィスト」と呼ばれる詭弁家たちだった。
人を信じ込ませ、扇動できればなんでもいい。自分を飾り、自分の利益のための「欺瞞の言論」が横行していたというのである。
池田氏もまたデマによる中傷、冤罪で攻撃され続けた。
四半世紀近くを経た今、当時は存在もしなかったSNSを通して、デマによる扇動は選挙結果さえ左右するほどの巨大な存在となって、社会を揺るがしている。
池田氏は、ソフィストだけでなく、ソクラテスの弟子のなかからも師を裏切る野心家が出てきたことを指摘している。
デマを煽る扇動家と、師を裏切る忘恩の野心家という構図は、ソクラテスの時代も今も変わらない。
こうした卑しい人間たちによって、ソクラテスは裁判にかけられる。罪状は、「国家の認める神々を認めず、新しい神格を導入している」「青年たちを堕落させている」というものだった。
ソクラテスは、幸福に満たされた生命で、安らかに息を引き取った。
しかし、師匠を奪われた弟子の衝撃は、あまりにも大きかった。プラトンは、心労のために病に倒れた。
そして――彼は心に決める。
「わが師の正義を、万人に示すのだ!」
弟子は、師匠を死に至らしめた社会悪との烈々たる闘争を開始した。この時、プラトンは二十代後半。八十歳で死ぬまでの五十年間、プラトンは、ただこの誓いを抱きしめて生き抜いたのである。
池田氏は最後に「ソクラテスの対話」について語る。それは、相手のなかにある「善いもの」を引き出し、互いを豊かにする対話だと指摘する。
ソ連の大統領だったゴルバチョフ氏は、終生の友人となった池田氏について「ソクラテスの対話を現代に蘇らせた方」(創価学会創立75周年に寄せた祝福のメッセージ)と評している。
「ソクラテスを語る」終わり→目次に戻る
「ナイチンゲールに負けてはいけない」(「ナイチンゲールを語る」)
「ナイチンゲールを語る」も、2002年1月から2月にかけて、「聖教新聞」紙上に全6回で掲載されたもの。
副題は「『女性の世紀』に寄せて」。かねて池田氏は、21世紀は女性が尊重され、女性の声が社会を変えていく「女性の世紀」であるべきことを提唱し続けてきた。
「近代看護の創始者」と呼ばれるフローレンス・ナイチンゲールは、19世紀、英国の裕福な上流家庭に生まれ、家族愛、容姿、教養、すべてを備えた、優雅な人生を過ごしていた。
しかし彼女は、苦しむ人々を救うため、当時、低く評価されていた看護の道に進んだ。
ナイチンゲールは芯の強い女性であった。
看護をわが道と決め、家族の反対はもとより、世間の偏見や無理解とも戦いながら、どんな障害にも屈することなく、自身の決意を貫くために「最善を尽くす」ことだけを続けた。
彼女がこれほどまでに強く生きることができたのはなぜか。池田氏は、その原動力は「高い使命を自覚していたから」だと語り、ナイチンゲールの次の言葉を引用している。
「使命感」をもたない看護婦が、自分の受持ち患者の呼び鈴の音と別の患者のそれとを聞き分けられるようになることは絶対にないであろう。(『ナイチンゲール著作集』1/現代社)
彼女が生涯、わが使命の火を燃やし続け、社会を変えることができたのはなぜか。それは人々と「団結」したからだと池田氏は語る。
正しい指導もなく、鍛えもなく、甘やかされるだけでは、多くの人は、いつしか堕落してしまう。勝手気ままな生き方は、幸福の軌道を外れ、結局、力のない敗北者の人生になってしまうものだ。(本書/以下同じ)
ナイチンゲールはクリミア戦争の現場に赴く。
病院のひどさは想像を絶した。収容人数をはるかに超える患者が、ネズミやシラミ、ばい菌が蔓延する狭い病室に押し込められ、あらゆる物資が不足する惨状が広がっていた。コレラやチフスも発生していた。
彼女はその只中に飛び込み、壮絶とまで言える看護を開始した。しかし、傲慢な軍医や将校たちは、看護婦たちをあからさまに蔑視し、ひどい待遇を強いた。偏見に溢れた彼らは看護婦が病室に入ることすら許さなかった。
そのような状況に対し、ナイチンゲールは「看護というものの意義を世に知らしめるに、またとない機会が到来した」と使命高く取り組んだ。いたずらに衝突するのではなく信頼を勝ち取る道を選んだ。
ナイチンゲールは戦場での保健衛生のあり方を抜本的に変えるべきだという信念に立つ。
しかし、それを声に出し、既存のあり方を変えることは至難だった。周囲からも大反対の声が上がった。
それでも、彼女は信念のままに行動していく。
池田氏は、ナイチンゲールが200もの著作を残していたことにも言及している。言葉の力で、ナイチンゲールは古い社会を変えていった。
終盤、池田氏は自分が創価学会に入会して間もない頃の思い出を語っている。1947年の話である。
戸田理事長の法華経講義が終わって、1人の若い女性が質問をした。信心していなくても立派な人はたくさんいることを、どう考えればいいのかと。
戸田先生は、温かく包み込むように、しかし厳然と、こう指導された。
「確かに、その通りです。そして、あなたは、いわゆる〝立派な人〟と比べれば、平凡な女性に見えるかもしれない。
しかし、あなたは、妙法という〝大法〟を持(たも)っている。これは大変なことなのです。妙法を持ち、人々に教えながら、広宣流布に生きゆく人生を送っていることは、最高の女性の生き方なのです」
そして戸田先生は、こう続けられた。
「大変に立派な活動を成し遂げ、立派な歴史を残したナイチンゲールのようには、あなたは、なれないかもしれない。また、なる必要もないかもしれない。しかし、その一念、精神だけは、ナイチンゲールに負けてはいけない」
「破門」によって世界から支持された文豪(「トルストイ」を語る)
「トルストイを語る」は、2002年12月、「聖教新聞」紙上に全5回で掲載された。
私は、晩年のトルストイの顔が好きだ。嵐の日も、雪の日も、毅然と、わが道を歩み通した勝利の顔。本当に、いい顔である。どうやって、あの顔になったのか――。
彼の波乱万丈の歩みをたどりながら、二十一世紀を生き抜く「人生の道」を見つめていきたい。(本書)
トルストイは1828年8月28日にロシアの名門貴族の四男として生まれた。ちなみに、池田氏はちょうど100年後の1928年1月に生まれている。
小説『幼年時代』が文芸誌に掲載され、トルストイが作家として認められたのは24歳のときだった。
ちょうどそのころ、クリミア戦争が勃発する。トルストイは最激戦地セヴァストーポリの砦に向かう。
この戦場で目にした凄惨な光景が、トルストイの強烈な原体験となった。その後、当時の「文明国」を見るために、ヨーロッパを旅する。しかし、そこで彼が見たのは残虐なギロチンであり、人間を見下す傲慢な態度だった。
一方、当時のロシアでは農民は「農奴」とされており、トルストイは領主として農奴を使う立場の家に生まれていた。
トルストイは、自身の土地での農民開放を政府に先立って実行した。彼は、人間扱いされていなかった農民の子供のための学校を作り、教壇に立った。教育に関する論文も多く残している。
結婚後、妻の献身的な応援を受け、本格的な文学の創作活動へと進んでいく。
彼は作品を通して、虐げられている民衆の偉大な底力を描き、愚かな戦争の虚しさを訴える。あらゆる幸福も名声も手に入れているように見えながら、じつは不幸な人生を生き、苦しむ姿。
トルストイは創作活動を通して「人間」を探究し続け、その結論として「生死」という生命の根本問題にたどり着き、やがて宗教・思想・哲学の探求へと進んでいく。
池田氏は、究極的には生死の解決の道は信仰しかないと断言する。すべての苦難を包含して勝利への力へと変換し、崩れぬ幸福境涯を作る。そのための信心である、と語る。
自分を変革することで、家庭が、環境が、そして世界が変革していく、これが「人間革命」の方程式である。
トルストイが次々と書き上げる小説は、社会を鋭く見つめている。民衆のなかに「生きた信仰」を見出したトルストイは、宗教が人間を抑圧し、手段として利用していることを見抜き、聖職者の欺瞞を厳しく告発した。
聖職者はトルストイの言論の力を封印しようと画策する。
作品が次々と発禁処分になる。しかし、国外では検閲削除されることなく作品が発表される。また、筆写や地下印刷などを通して世界的に広まっていった。
最終的に、教会はトルストイを一方的に「破門」にした。権力に溺れた聖職者たちの常套手段でもある。
しかし、この「破門」によって、世界はトルストイを〝権力悪と戦う良心〟として支持した。
その1人が若きガンジーであった。そして南アフリカから帰国し、インドで命懸けの非暴力闘争を繰り広げたガンジーに感銘し、立ち上がった青年がいる。アメリカの公民権運動の指導者キング博士である。
池田氏は、この史実を通して、魂のバトンを受け継ぐ者がいれば「正義の道」も「真実の道」も滅び消えることはないと綴る。
「トルストイを語る」終わり→目次に戻る
苦悩を突き抜けて歓喜に至れ(「ベートーベンを語る」)
「ベートーベンを語る」は、池田氏が折々に紙誌に記した文章から抜粋して再構成された。
終戦後の殺伐とした時代のなかで、若き池田氏は「大森の薄汚れたアパートの一室」に暮らしていた。
否、夜は閉じ込められていたというほうが、私の精神状況には適切な表現かもしれない。給料も安い。そのうえ、胸を病んでいた。このままではと、死の予感すらある日もあった。(本書/以下同じ)
そんななかで、渇(かつ)して泉を求めるように音楽を求め、なけなしの財布をはたいて蓄音機を買い、レコードを聴いたという。
ベートーベンの「運命」が、狭い一室に轟然と響きわたった時、その力強く厚い音の真っ只中に陶然として聴き入った感動は、今も鮮やかである。わずか三十分たらずの演奏だったが、私の人生にとっては、たしかに大事件であった。
ベートーベンは、池田氏が各種スピーチや講演でもっとも多く言及してきた人物の1人であろう。
1981年5月にオーストリアを訪問した際には、かつてベートーベンが暮らしたという土地の田舎道を歩き、記念館(現・ベートーベン博物館)にも足を運んだ。
ベートーベンが耳の異常に気づいたのは、20代半ばのことだった。音楽家にとって何より大事な聴力が悪化していく。
記念館の中庭にリンゴの木があった。それはベートーベンが自分を慰めるために植えたリンゴの木のうち。生き残った1本だという。
生き残ったリンゴの樹――。
ベートーベンも生き残った。
何か偉大な貢献をして死ななければ、死にきれなかったのだ。苦しくとも、このどん底から、生きていこう。使命を果たし、果たし終わってから、死ねばよい!
「善きことを一つでもできるうちは、勝手に人生から離れてはならない」。本で読んだその言葉が、彼を自殺から引きとめた。
池田氏は、ベートーベンを愛したのみならず、その楽曲を繰り返し民衆のなかへと広げた。
1990年11月16日の第35回本部幹部会で、その3年前の年末に創価学会学生部の結成30周年を記念する「第九」の演奏会に出席したことに触れつつ、池田氏はこうスピーチした。
そこで一つの提案として、創立六十五周年(一九九五年)、創立七十周年(二〇〇〇年)には盛大に、「第九」の合唱を行ってはどうだろうか(拍手)。具体的な方法や内容については検討していただくことにして、壮麗なる世界広宣流布の前奏曲として、後世に残しておきたい。
翌月の12月16日。折しもベートーベンの誕生日にあたるこの日、第36回本部幹部会の席上でも、大田区混声合唱団によって「歓喜の歌」の合唱が披露された。
じつはこの同時期、日蓮正宗から創価学会に「お尋ね」と題する文書が届く。そこにはベートーベンの「歓喜の歌」をドイツ語で歌うことは〝外道礼賛〟であるという目を疑うような非難の文言が記されていた。
池田氏は古今東西の名著や人物論を通し、あるいは世界的な学識者との対談を通し、創価学会員に普遍的な価値観と視野を育んできた。
これに対し、当時の宗門がベートーベンを歌うことが〝外道礼賛〟にあたるとして、これを池田氏を追放する理由の1つに挙げてきたことは、日蓮正宗の出家たちの無教養さと異常さを象徴している。
1991年11月、ついに日蓮正宗は創価学会に「破門通告書」を送り付けた。けれども、世界中の創価学会員は出家たちの狂態を笑い飛ばし、〝魂の独立〟を喜び合った。
当時、創価学会の会合では「歓喜の歌」のメロディーに乗せた「創価歓喜の歌」が高らかに歌われた。
ベートーベンは、創価学会にとって、邪悪な宗教的権威の魔の手を打ち破る大きな力となったのである。
1994年11月23日。福岡ドーム(当時)で「アジア青年平和音楽祭」が開催され、九州青年部5万人が「第九交響曲」の「歓喜の歌」を合唱した。
巨大なドーム球場で5万人が音をずらさずに合唱するという不可能と思われた前代未聞の壮挙をなしとげたのである。
合唱が最高潮に達した瞬間、開閉式のドームの天井が開き、天空から太陽の光が神々しく射し込んだ。
2001年12月2日には、九州の117会場を衛星中継で結び、10万人の九州青年部が「歓喜の歌」を合唱した。
それは、恩知らずで残忍な出家たちの横暴に対する、青年たちの勝鬨の歌声となった。
2005年2月の本部幹部会で、池田氏はこう語った。
音楽の英雄である楽聖ベートーベンの言葉を、「信心の英雄」「広宣流布の英雄」である皆さんに贈りたい。
「どんなことがあっても運命に打ち負かされきりになってはやらない。――おお、生命を千倍生きることはまったくすばらしい!」(ロマン・ロラン『ベートーヴェンの生涯』片山敏彦訳、岩波書店)
生前のベートーベンは、いくつもの病気を抱え、経済的にも困窮し、周囲からの妬みと誹謗中傷に晒され続けた。
池田氏は「苦悩を突き抜けて歓喜に至れ」というベートーベンの言葉を、幾度となく語ってきた。池田氏の人生そのものが、あらゆる艱難を打ち破って、人間の可能性の高みを証明する95年間であった。
2003年、欧州連合(EU)で憲法が制定され、ベートーベンの「交響曲第九番」最終楽章の「歓喜の歌」が、「EUの歌」として明文化されている。
「ベートーベンを語る」終わり→目次に戻る
『歴史と人物を語る』(上・下)
池田大作著/第三文明社/定価 各1,500円(税込)
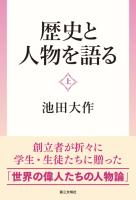
「本房 歩」関連記事①:
書評『ヒロシマへの旅』――核兵器と中学生の命をめぐる物語
書評『アレクサンドロスの決断』、『革命の若き空』(同時収録)
書評『新装改訂版 随筆 正義の道』――池田門下の〝本当の出発〟のとき
書評『希望の源泉 池田思想⑦』――「政教分離」への誤解を正す好著
書評『ブラボーわが人生4』――心のなかに師匠を抱いて
「池田大作」を知るための書籍・20タイトル(上) まずは会長自身の著作から
「池田大作」を知るための書籍・20タイトル(下) 対談集・評伝・そのほか
書評『創学研究Ⅱ――日蓮大聖人論』――創価学会の日蓮本仏論を考える
書評『公明党はおもしろい』――水谷修が公明党を応援する理由
書評『なぎさだより』――アタシは「負けじ組」の組員だよ
書評『完本 若き日の読書』――書を読め、書に読まれるな!
書評『新版 宗教はだれのものか』――「人間のための宗教」の百年史
「本房 歩」関連記事②:
書評『人はなぜ争うのか』――戦争の原因と平和への展望
書評『見えない日常』――写真家が遭遇した〝逮捕〟と蘇生の物語
書評『歌集 ゆふすげ』――美智子さま未発表の466首
書評『法華経の風景』――未来へ向けて法華経が持つ可能性
書評『傅益瑶作品集 一茶と芭蕉』――水墨画で描く一茶と芭蕉の世界
書評『もし君が君を信じられなくなっても』――不登校生徒が集まる音楽学校
書評『LGBTのコモン・センス』――私たちの性に関する常識を編み直す
書評『現代台湾クロニクル2014-2023』――台湾の現在地を知れる一書
書評『SDGsな仕事』――「THE INOUE BROTHERS…の軌跡」