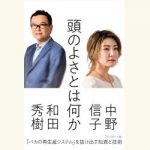政府与党連絡会議の終了後、記者団に答える山口代表(2月6日)
64%が同性婚や理解増進法に賛成
2月3日夜に飛び出した首相秘書官によるLGBTQ+や同性婚への差別的発言は、むしろそのような差別はもはや許されないのだという現下の世論を可視化させた。
この発言を受けて、共同通信社は2月11~13日に全国緊急電話世論調査を実施。
同性婚を認める方がよいとの回答は64.0%で、認めない方がよいの24.9%を大きく上回った。(「共同通信」2月13日)
LGBTなど性的少数者への理解増進法が必要だとの答えは64.3%に上った。(同)
同性婚に賛成と回答した39歳以下の若い世代は81.3%に達していたと共同通信は伝えている。
岸田首相は「今の内閣の考え方には全くそぐわない言語道断の発言だ。『性的指向』や『性自認』を理由とする不当な差別や偏見はあってはならない」と述べ、差別発言をした秘書官を翌日のうちに更迭。さらに自民党幹部にLGBT理解増進法案を今国会に提出するよう指示した。
この法案は2021年5月に自民党を含む超党派の議連で一旦は合意にこぎつけながら、自民党内保守派の強硬な反対で国会提出が見送られたものだった。 続きを読む