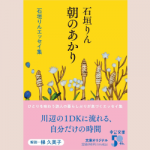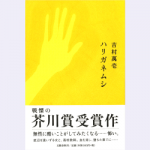「政教一致」体制と戦ったのが創価学会
――池田名誉会長が2010年5月を境に公の場に出ることを控えたことについて、さまざまな人間や媒体が勝手な憶測を書き散らしてきました。今般の逝去に際しても、あいかわらず単なる憶測や出所不明の話を書いている論者が見受けられますね。
青山樹人 なかには学者やジャーナリストを名乗りながら、名誉棄損になるような話を平然と書いたり語ったりしている人物もいます。池田先生は2015年も創価大学で居合わせた学生たちを激励していますし、16年も埼玉や八王子を訪問しています。17年も創価大学や神奈川、東京牧口記念会館を訪問しています。18年に長野研修道場で『新・人間革命』を脱稿した折は、研修道場内で何十人もの会員と間近で会っています。その様子は聖教新聞でもカラー写真で報じられています。
19年には長野研修道場の他、落成した世界聖教会館を2度訪問して勤行されました。21年10月には修学旅行に来ていた関西創価小学校の6年生たちと、創立者として都内で会っていますね。22年に入っても夫妻で恩師記念会館を訪問して勤行されています。
そういえば、『第三文明』2月号で作家の佐藤優氏が、『週刊新潮』に寄せた宗教学者の島田裕己氏のコメントについても痛烈に批判していました。島田氏は〈池田氏は最期まで宗教の本質である〝死〟についての解を提示できなかった〉〈死について掘り下げることがないまま、表舞台から去っていった。そこに宗教者としての限界があった〉等とコメントしていたのです。
佐藤氏は、ハーバード大学での講演や『法華経の智慧』で展開された先生の死生観に触れ、〈宗教学者であり、創価学会についての著作も少なくないにもかかわらず、島田裕己氏は最重要著作の1つである『法華経の智慧』すら読んでいないのでしょう。底の知れたものです。〉と一刀両断しています。 続きを読む →