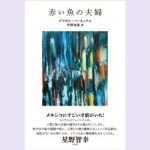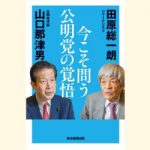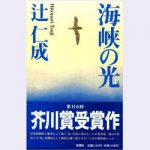東京というメガロポリスに住んでいると、自然と接する機会が少ないようにおもわれる。人間以外の生物といえば、烏と鼠。あとはゴキブリだ。ペットもいる。犬と猫は、人間の生活に同化しているので、なかば人間のようにおもわれがちだが、やはり、内部には野生=自然をかかえている。自然との共生がいわれるが、本来、人間も自然の一部である。いくら医療技術や科学が進んでも、僕らの身体が自然から切断されることはないだろう。
おもしろい短篇集を読んだ。『赤い魚の夫婦』。作家はメキシコ人の女性で、グアダルーペ・ネッテルという。「赤い魚の夫婦」「ゴミ箱の中の戦争」「牝猫」「菌類」「北京の蛇」と5篇の短篇小説が収められている。
どの作品にも、人間ではない生物が登場する。金魚、ゴキブリ、猫、菌類、蛇――それぞれが登場人物と関り、独自な世界を築き上げていく。なかでも、「菌類」は秀逸だ。 続きを読む