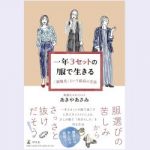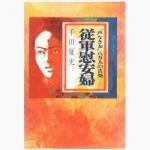第52回 正修止観章⑫
[3]「2. 広く解す」⑩
(8)陰入境を観ず・入境を明かす②
「陰入境を観ず」・「入境を明かす」(※1)の段落の続きである。今回の範囲では、まず九種の五陰を取りあげている。『摩訶止観』巻第五上には、
一期(いちご)の色心を果報の五陰と名づく。平平(びょうびょう)の想受は、無記の五陰なり。見を起こし愛を起こすは、両(ふた)つの汚穢(おえ)の五陰なり。身口の業を動ずるは、善悪の両つの五陰なり。変化示現は、工巧(くぎょう)の五陰なり。五善根の人は、方便の五陰なり。四果を証するは、無漏の五陰なり。是の如き種種は、源は心従り出ず。(第三文明選書『摩訶止観』(Ⅱ)、550頁)
と述べている。これは、『大乗義章』巻第八、「次に三性に就いて、五陰を分別す。三性と言うとは、所謂る善・悪・無記性なり。『毘曇』の如きに依るに、陰に別して九有り。相従して三と為す。言う所の九とは、一に生得の善陰なり。二に方便の善陰なり。三に無漏の善陰なり。四に不善の五陰なり。五に穢汚(えお)の五陰なり。六に報生の五陰なり。七に威儀の五陰なり。八に工巧の五陰なり。九に変化の五陰なり(底本の注記の校異によって「九変化五陰」を補う)」(大正44、 623下6~11)とほぼ共通である。 続きを読む