2008年に沖縄空手の有力4団体で結成された連合組織・沖縄伝統空手道振興会(豊見城市)。これまで各種国際セミナーの開催をはじめ、沖縄空手会館の運営などにも携わってきた。このほど喜友名朝孝・前理事長の任期を引き継ぎ、歴代4人目の理事長に就任した北中城村(きたなかぐすくそん)の新垣邦男(あらかき・くにお 1956-)村長に、振興会の今後の課題などについて聞いた。(取材 2019年6月27日) 続きを読む


2008年に沖縄空手の有力4団体で結成された連合組織・沖縄伝統空手道振興会(豊見城市)。これまで各種国際セミナーの開催をはじめ、沖縄空手会館の運営などにも携わってきた。このほど喜友名朝孝・前理事長の任期を引き継ぎ、歴代4人目の理事長に就任した北中城村(きたなかぐすくそん)の新垣邦男(あらかき・くにお 1956-)村長に、振興会の今後の課題などについて聞いた。(取材 2019年6月27日) 続きを読む

日本経済新聞が6月に実施した世論調査で、興味深い数字が示された。
安倍政権に対する支持率が、60歳以上では49%にとどまったのに対し、20代では70%に達したのだ。
この世代間の支持率の乖離は、とくに2017年以降、15ポイント以上の開きを生んでいるという。
その背景として同紙は、29歳以下の世帯収入が上昇していることや、「幸福度」の上昇を指摘している。 続きを読む

1億3000万円。これは、1人の参議院議員が1期6年間に国から受け取る歳費と期末手当のおよその合計額だ。
実際には、これに文書通信交通滞在費と、政策担当秘書、公設第一秘書、公設第二秘書の3人の給与として6年間で約1億8000万円が加わる。
つまり、1人の参議院議員の1期6年間の政治活動には、3億円以上の税金が使われるのだ。そして、参議院には「解散」がないので、どんな人間も当選してしまえば6年間、身分が保証される。
この支出に十分に見合うだけの能力を持ち、見合うだけの仕事をする議員を選ばなければ、ツケを払わされるのは国民である。 続きを読む

人間の生命に対する政治の〝感度〟。それがもっとも象徴的にあらわれる場面が「災害」だ。
公明党は、今回の参議院選挙の公約として、「防災・減災・復興を社会の主流に」を掲げた。
「一人の生命を守り抜く」ため、 公明党は、「防災・減災・復興」を政治の主流に位置付け、 防災意識を高める教育に全力を挙げ、「社会の主流」に押し上げていきます。 あらゆる知恵を総動員し、世界一災害に強い「防災大国」を構築します。(公明党「参院選2019 マニフェスト」)より
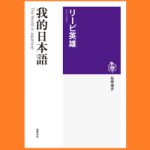
リービ英雄さんとは、文芸家協会でときどき顔を合わせる。最初にお眼にかかったとき、「村上政彦です」と名刺を出したら、「お名前は、よく存じ上げております」と丁寧な日本語で返されて驚いた。
彼は、北米で生まれ育ったアメリカ人だ。17歳で日本語と出会って、大学で『万葉集』を学び、それを英訳して、北米でもっとも権威のある全米図書賞を受けた。その後、日本語で小説を書くようになり、作品は高く評価されている。 続きを読む