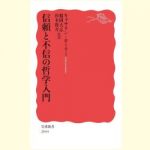個人と社会に対する大きな影響
信頼がもつ大きな力とその複雑さを改めて知ることができる一書である。
食事をする。通勤電車に乗る。買い物をする。わたしたちの普通の生活を支えている基盤が信頼である。信頼なくしては何もできない。しかし「信頼とは何か」を説明することはじつに難しい。わたしたちは信頼をあたかも空気のように自明のものと考えているので、そこに潜む問題にはなかなか気づくことができない。
著者のキャサリン・ホーリー(1971~2021年)は信頼の哲学の分野で、研究を大きく進展させたことで知られている。本書は一般の読者向けに書かれた信頼の哲学入門である。
しかし多くの社会科学者は、「高信頼」あるいは「低信頼」の社会で生活することの影響が、個人と個人の関係を超えて、あらゆる人に影響を与えるとも考えている。「ソーシャル・キャピタル」は物理的資本(装備)や人的資本(スキル)と並び、社会の生産性を高めたり低めたりする資源に位置づけられている。(本書36ページ)
近年の研究成果では、信頼は個人だけではなく、多くの人に強く影響するとされている。互いの信頼が高い集団では生産性が高まり、所属する多くの人々に経済的恩恵をもたらす。それに対して、集団内の不信が強いと説明責任などが過剰に求められ、本来は他のことに使えるはずだった時間と資源を浪費してしまうという。
たとえば、雇用主が従業員の仕事を監視しすぎる会社では、従業員は信頼を受けていると感じなくなり、能力を十分に発揮できなくなり、会社へ貢献しようとする意欲も弱まる。また、大企業が発注先の下請け会社から高い信頼を受けている場合、情報の共有などが進み、交渉労力も削減される。
信頼にはものごとを円滑に進め、効率的に利益を増大させる作用がある。信頼が高い社会はそれだけ幸福な社会になる。信頼がソーシャル・キャピタル(社会関係資本)と位置付けられる理由もここにある。
信頼が生まれる状況とは
そして信頼は、わたしたちの日常生活の中で誰もが遭遇し、また見逃してきたものである。当然、信頼にはさまざまな捉え方があり、文脈が異なれば、それに応じて信頼のさまざまな側面が重要になる。しかし、そのすべてを貫く重要な考え方がいくつかある。すなわち、人や組織に対する信頼は通常、無生物に対する信頼よりも豊かであり、コミットメントは果たされるだろうという期待を伴う。(本書22ページ)
信頼に関する研究は、経済学、社会学、生物学、心理学など、多くの学問領域でさまざまに行われて来たが、それは2つに大別できるという。
(1)信頼は合理的自己利益から生まれる。
(2)信頼は互恵的利他主義から生まれる。
しかし、これらは利害関係からしか信頼を見ておらず、その豊かさや複雑性を捉え損ねてしまう。わたしたちが「この人は信頼に値する人物だ」という評価をするとき、そこには道徳的賞賛や尊敬などの感情も含意される。損得勘定だけで判断すると考えるのは、あまりにも一面的である。
では信頼とは何か。どこから生まれるのか。著者は信頼を人間のコミットメントから生まれるとする。
コミットメントとは、ある行為を義務や責任をともなう形で引き受けることである。ある人がコミットメントを果たすと考えればその人を信頼し、コミットメントを果たすことができないと考えれば不信を抱く。
ここで決め手となるのが意図と能力だ。
どんなに能力がある人でも、悪意の人を信じてしまえば、騙され食いものにされる危険がある。また善意がある人でも、能力がなければ請け負った行動を果たすことはできない。
自分が周囲から信頼される人間になりたい場合もこの視点は有効だ。自分の能力を超えた行為を引き受けると、善意があったとしても結果として信頼を損なってしまう。だからこそ、安易な安請け合いは禁物なのである。
より良く信頼する人になる
不信と、信頼の欠如を強調することは屁理屈のように思われるかもしれない。しかし、この区別は信頼に関わるわたしたちの道徳判断にとって中心をなすものである。誰かに不信を抱くということはその相手を低く評価することであり、些細なことであれ、何か悪いことをしていると考えることになる。(本書17ページ)
著者の学説の特徴は不信の役割を明快に説明した点にある。
これまでの多くの研究では、不信は単なる信頼の欠如とした。しかし信頼の欠如と不信は同じものではない。電車でとなりの席に座った人をわたしたちは信頼しないが、かといって不信の念をもつことはない。ある人物に対して不信をもつ場合には、「このような人とは金輪際かかわりをもちたくない。こんな人間にはなりたくない」という人格や道徳的非難はもとより強い否定的感情さえも伴う。
過度な不信は、疑心暗鬼を生み出すだけではなく社会的な利益も減少させる。だが、適切な不信は生きていくうえで重要な役割を果たす。嘘や搾取を見抜くことを可能にし、危険な人間関係からわたしたちを遠ざける。
〝信頼に値する人間には信頼を、不信に値する人には不信を〟とは、本書のなかで幾度も繰り返えされるフレーズである。
わたしたちの信頼や不信は、個人の精神だけでなく、社会的利害にも直結する影響力をもつ。だから、その判断には大きな社会的な責任が伴っていることを知らなければならない。
たとえば、信頼に値する会社や組織、政治家を信頼すれば社会的利益が生まれ、より信頼が強まる好循環が生まれる。しかし、信頼に値しない会社や政治家を信頼してしまえば、混乱と猜疑心が生まれ、社会的利益は減少する。不信が強化される負の循環に陥ってしまう。
周囲から信頼に値する人間とみなされ、より良く信頼する人になろうとするなら、自己を知り、他者を知らなければならない。それは〝汝自身を知る〟という哲学の根本的テーマへとつながっていく。
「信頼とは何か」という身近で素朴な疑問は、幸福な人生とより良い社会の実現を目指すうえで、避けては通ることのできない、きわめて重要な問題なのである。
『信頼と不信の哲学入門』
(キャサリン・ホーリー著、稲岡大志、杉本俊介訳/岩波新書/2024年12月20日刊)
関連記事:
「小林芳雄」記事一覧