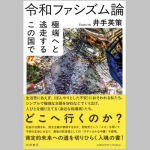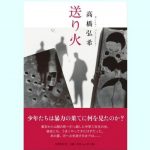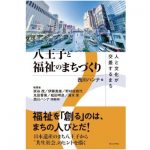なぜ財政史が重要か
著者の井手英策氏は、弱者を生み出さない社会政策「ベーシックサービス」の提唱者として知られている。本書は、戦前の日本とドイツの財政史をたどりながら、現在の日本社会が陥っている危機の本質を探り当て、その克服の方途を探ったものである。
よくおぼえておいてほしい。
財政とは社会をうつしだす鏡である 。この本は、経済史でも、政治史でも、社会史でもなく、財政史という一風かわった、そして多くの研究者が使いこなせなかったメスをもちいて、日本社会の病根をえぐりだしていく。(本書13ページ)
著者はなぜ、ふだんあまり耳にすることの財政史という視点にあえてこだわるのだろうか。そもそも財政という用語はなにを意味するのか。
現在、世界の多くの国々は民主主義といわれる社会体制のなかで暮らしている。労働の対価として収入を得て、市場からモノやサービスを購入することによって生活を営んでいる。だが得られる収入には格差があり、また病気やケガなどの理由で働くことのできない人も存在する。こうした状況を放っておけば、弱肉強食の世の中になり、共同体は分断され、社会的秩序は崩壊してしまう。 続きを読む