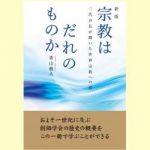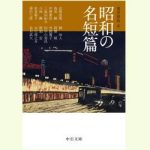《「東京都にパートナーシップ制度を求める会」山本代表と懇談する都議会公明党の高倉氏ら(2021年6月8日付「公明ニュース」より)》
全国初、オンラインでの申請と発行
11月1日、東京都は「パートナーシップ宣誓制度」を開始した。
この制度は、LGBTQなど性的マイノリティのパートナーシップ関係を東京都が公認するもの。
対象となるのは、以下の要件をすべて満たしているケースで、国籍は問わない。
●「双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者である」と宣誓したこと。
● 双方が成年に達していること。
● 双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと、かつ、双方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
● 直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係にないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組により当該関係に該当する場合を除く)。
● 双方又はいずれか一方が「都内在住、在勤又は在学」であること(都内在住については、双方又はいずれか一方が届出の日から3か月以内に都内への転入を予定している場合を含む)。
申請から受理証明書の発行まで、全国で初めてオンラインで可能となった。すでに10月11日から申請受付が始まり、制度開始の11月1日時点で177組が申請したという。 続きを読む