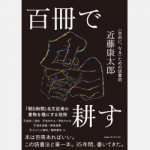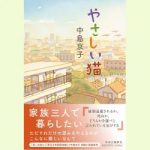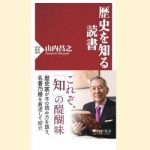僕は小説家としてプロデビューしてから35年になるけれど、いまだに文章の書き方や読書の仕方についての本を読む。ひとつは、同業他社がどのような働き方をしているか知りたい好奇心、もうひとつは、まだ僕自身が気づいていないやり方があれば学びたいという向学心。
結果として、たいてい文章の書き方の本は、あまり発見がない。ああ、同じことをやっているな、と市場調査で予想通りのデータが示されたという思いになる。読書の仕方についても、似たようなものだ。
ところが、ここで取り上げる『百冊で耕す』は、ちょっとおもしろかった。僕は好きな作家の吉田健一が、300冊の蔵書しか持たなかったと知って、これは僕も実践しなければと思った。
吉田健一の300冊であれば、とても貴重な本ばかりだろう。蔵書リストが見たいぐらいだが、それは叶いそうもない。そこで、吉田健一になったつもりで、少なくとも4~5000冊はある蔵書(それも日々、増え続けている)を必要な本だけに絞ろうと考えた。 続きを読む