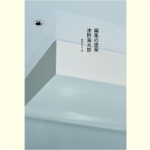「創価学会は正典化を完成した」
――前回は、池田名誉会長が80歳以降の展望として「随筆 新・人間革命」第1回で綴った「妙法に説く不老不死のままに、永遠に広宣流布の指揮をとることを決意する」について、それは後継の弟子が陸続と登場することによってのみ実現されるのだということを確認しました。名誉会長は早い時期からはるか未来までを見通して、あらゆる手を打ってきたわけですね。
青山樹人 池田先生がこの随筆を発表されたのは1998年1月4日付の聖教新聞でした。これが、どういう時期であったかを確認しておきたいと思います。
1990年の暮れに、当時の日蓮正宗法主らが奸計をめぐらせて、いわゆる第二次宗門事件が惹起します。池田先生を総講頭から罷免して創価学会を動揺させて解体し、黙って供養を差し出す従順な信徒だけを囲い込もうと謀ったわけです。その目論見のなかで91年11月に宗門は創価学会を〝破門〟します。
ところが、学会はビクともしなかった。もともと学会は1952年9月に宗教法人の認証を得ている団体です。むしろ怪しげな「法主信仰」に教義を変質させた宗門のほうから袂を分かってくれたことは、その後の創価学会が一気に世界宗教化する好機となりました。 続きを読む