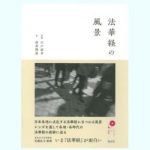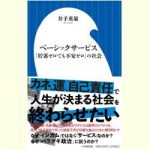外交戦略としての四天王寺
鳳書院が展開する新シリーズ「アジアと芸術」の第3弾として刊行された。地理的には東北から九州まで、時間的には7世紀から現代まで、日本各地に点在する「法華経ゆかりの風景」を120点余の写真と12本のエッセーで描き出す。
巻末には、日本思想史研究の第一人者であり、「日本学」の研究者としても国際的に著名な、佐藤弘夫・東北大学名誉教授による「解説」が掲載されている。
冒頭は「奈良と大阪」で、聖徳太子が創建した法隆寺と四天王寺。日本一の超高層ビルである高さ300メートルの「あべのハルカス」展望台からは、眼下に四天王寺の伽藍が一望できる。林立するマンション群に囲まれ、そこだけ緑の木々で区切られた四天王寺の姿は、まるで現代と古代が混然一体となったかのようだ。
7世紀の初めに創建されたと伝えられる四天王寺は、いくたびか戦火に見舞われ、ことに第二次世界大戦の空襲で灰燼に帰した。今日の伽藍は、創建当時と同じ位置に、同じ配置で再建されたもの。 続きを読む