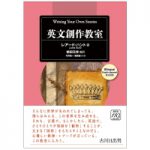1970年代以降、日本本土を席捲した極真空手――。型よりも組手を重視し、実戦カラテを標榜することで、劇画や映画を通して若者を中心に爆発的なブームを巻き起こした。今回から3回にわたり、フルコンタクト空手を経て沖縄伝統空手に魅せられた3人の空手家を紹介する。1回目は、極真空手がまだオープントーナメントという全国規模の大会開催を行ってまもないころ、沖縄空手の本場から単身で極真に乗り込んだ経験をもつ金城健一館長(琉誠館)に迫る。 続きを読む


1970年代以降、日本本土を席捲した極真空手――。型よりも組手を重視し、実戦カラテを標榜することで、劇画や映画を通して若者を中心に爆発的なブームを巻き起こした。今回から3回にわたり、フルコンタクト空手を経て沖縄伝統空手に魅せられた3人の空手家を紹介する。1回目は、極真空手がまだオープントーナメントという全国規模の大会開催を行ってまもないころ、沖縄空手の本場から単身で極真に乗り込んだ経験をもつ金城健一館長(琉誠館)に迫る。 続きを読む
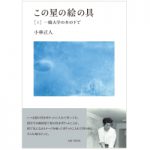
手のひらにすっぽりおさまる小さな本。白地のカバーに四角い青が浮かぶ。
著者は小林正人氏。世界的に名の知れた画家である。国際展の中でも古い歴史をもつサンパウロ・ビエンナーレでは、日本代表として作品を展示した。
長年にわたって色やかたちと徹底的に向き合ってきた一人の画家が言葉を手にしたとき、できあがったのは単なる絵画論ではなかった。それは自然と「小説」の体裁をとった。 続きを読む


コンクールの表彰式(北京市内)でスピーチする陳文戈氏
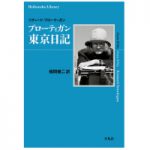
小説を読むようになったころ、手に取ったのは、最初のうちはヨーロッパの近代小説だった。やがてモダニズムの作品に親しむようになって、気づいたらアバンギャルドへたどりついていた。
いちばん気に入ったのは、フランスのヌーボーロマンだ。代表的な作家であるアラン・ロブ=グリエの作品を追いかけた。彼の作品で手に入るものは、すべて読んだ。といってもフランス語は読めないので、翻訳されたものに限る。 続きを読む