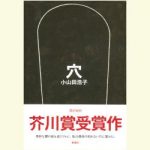各国で続く選挙への介入工作
参院選の公示日を翌日に控えた7月2日、日本経済新聞が「ロシアによる情報工作の影が日本でも広がってきた」と警告する記事を掲載した(『日本経済新聞』7月2日)。
7月15日午前、平将明デジタル大臣はオンライン会見で、「参議院選挙とSNS」についての記者からの質問に答え、次のように語った。
外国においては、他国から介入される事例なども見て取れるので、今回の参議院選挙も一部そういう報告もあります。検証が必要だと思いますが、そういったことも注意深く見ていく必要があるのだろうと思っています。(デジタル庁HP「大臣会見」)
昨年12月、ウクライナの隣国であるルーマニアの憲法裁判所は、11月におこなわれた同国の大統領選挙の結果を「無効」とする判断を下した。
無名の候補者ジョルジェスク氏が本命視されていた首相の得票を上回る結果になったのだが、TikTokなどで外国勢力の介入による情報操作の疑いが浮上したためだ。 続きを読む