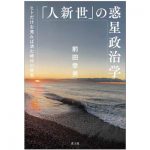明治から令和へと思想史的時空間軸において、優に百年を超えたこの現代。地球規模に拡がる気候危機時代における気候正義教育と創価世界市民教育のための洞察の一書と思料される著作に出会うことが出来た。前田幸男著『「人新世」の惑星政治学-ヒトだけを見れば済む時代の終焉-』(青土社、2023年)は、まさに今日の時宜を得たものと考えられる。
この混迷の世界に臨み、翻って地人相関哲理に通暁された牧口常三郎先生著『人生地理学』から謹んでの位相と相関の視座から、同著につき寄稿書評させていただけることに第三文明社編集部のご高配に深謝いたしたい。
1.はじめに
1903年に初版が刊行された牧口常三郎先生の『人生地理学』は、明治日本の地理教育における生命文明視点の改革のための警醒の書とも思料される。いわば「人間生命文明学」と「世界情勢地理学」の有機的関係までも論じている稀有の書と勤考させて戴くものである。また、この2026年には発刊から123年を迎えるところ、その根幹思想は今なおこの地球上のグローバルな課題についてもその生命文明的視座により、当時において既に現下の地球規模の諸問題対立を止揚されているものと拝察申し上げるものである。これらを踏まえ、以下のとおり前田幸男著『「人新世」の惑星政治学―ヒトだけを見れば済む時代の終焉―』につき、牧口先生の『人生地理学』から123年の位相と相関の視座より僅かながらの書評をさせて戴ければ幸いである。
近年、地球環境の気候危機、核戦争危機も含め、いわゆる「人新世=Anthropocene」における地球規模課題に対し、惑星政治学的視座からの再定位が求められていると考えられる。こうしたなかで「人生地理学」と「地球という惑星の危機課題」の時空間対話に取り組まれたのが前田幸男著『「人新世」の惑星政治学』であると思料される。
本稿においては、前田教授の惑星政治学思想を、牧口先生の『人生地理学』といういわば地球生命尊厳思想の源流にさかのぼり、「位相」と「相関」という観点で思料することで、その交差から浮かび上がる現代的地球規模課題を掘り下げる切掛けを紹介できれば幸いである。そして牧口先生の『人生地理学』(1903年)の発刊から123年を経た現在、近代日本の教育思想と現代の惑星政治思想との架橋の予備的試みへ何らかよすがとなればと願うものである。
前田教授による『「人新世」の惑星政治学』は、人新世における政治主体と地球環境の相関的再構築を目指す政治思想学的試みであり、その内容は牧口先生の『人生地理学』から現代へ向けた位相的展開とも考えられる。そこにおいて共通する構造──すなわち、人間と地球環境、教育と国際政治における連関──に着目し、その理論的親縁性と現代的意義を、地球環境危機の時にあたり、寄稿させて戴けることに心より深謝いたしたい。
2.前田教授の『「人新世」の惑星政治学』とノンヒューマンの惑星的相関論
前田教授は人新世の惑星政治学という地球規模の時代診断を提示し、従来の主権国家、経済中心主義を越えた新たな国際政治学思想の再構築を試みている。中心に据えるのは、惑星政治学という政治学的リアリズムの概念であり、それはヒトとその取り巻く地球全体生態系というノンヒューマンの惑星的相関構造のなかで生成される地球環境の多層的な概念であると思料される。
ここで考えられるのは、いわゆるヒトの存在だけでなく、ノン・ヒューマンの存在(地球環境・地質・植物・動物・微生物等の生態系)も含んだ相互依存的ネットワークである。これを前提とした新たな政治的行為の主体が、人新世において求められているものと思料される。すなわち、地球のプラネタリー・ヘルスの国際政治学による対象化とも捉えられ、共感と責任に根ざした新しい国際政治学が志向されていると考えられる。
『人生地理学』と『惑星政治学』という一見、時代も文脈も異なるようにみえる両著であるが、「位相と相関」という関係性思考を中核に据え、改めてそれぞれを読むとき、その深い親縁性の存在に気づかされる。
牧口先生は、教育とは自己と郷土と世界地理の相関性の深化でもあるとされたと考えられ、これを倫理の課題としたとも拝察するものである。前田教授は、地球の多様性の関係のなかから生まれる多層的主体概念を課題としており、人間と惑星としての地球の関係は生命の尊厳という倫理的選択によって共存可能となることを考察しているものと思料される。
とりわけ牧口先生がその著『人生地理学』で示されている地人相関は、地理的条件(地)と人間主体(人)の相即不離の相互作用を単なる物理的環境論に留まらせず、文明的・教育的相互形成関係へと昇華させておられることにおいて傑出された洞察が拝察されるものである。この地人相関の稀有の動的相関性理解は、現代的には地球生態学的相互構成性とも接続可能であり、前田教授のダイナミックな惑星的地人相関概念とも理論的親縁性をもつものと考えられる。
とくに、牧口先生のご思想の根底には、もっとも含意ではあると思料されるものの、「依正不二」──すなわち人間(正報)と環境(依報)は本質的に一体であり、どちらかが他を決定するのではなく、相互に相即不離であるという考え方がすでに自然に貫かれていたと思料される。この観点は、現代の国際政治哲学においても、地球環境を顧みないヒト中心状態からの脱構築や地球環境との関係の倫理性へと接続されうる視座であり、前田教授が考察されている地球の自然生態系についての倫理的な国際政治哲学上の再構成の理念と響き合うものと思料される。
さらに、前田教授が『「人新世」の惑星政治学』の中核に据えていると考えられる「センス・オブ・ワンダー(sense of wonder)」の思想的意義は見逃せないものであると思料される。これは、人類が自己の利害を超えて自然世界そのものに生命的に畏敬を覚える能力を回復するという倫理的な人類教育学的契機ともなるのではなかろうかと思料される。この観点は、牧口先生の地理学教育が単なる知識伝達ではなく、自然環境との関係性を通じた人格形成を志向していたことと軌を一にするものと推察される。
「『人新世』の惑星政治学」が瞠目されるのは、「地理教育」や「国際政治学」を固定的制度として捉えるのではなく、「関係を組み替える力」として理論化しようとする点である。まさにこの思想は、ユネスコのグローバル市民教育(GCED)における「変革的学習(transformative learning)」にも通じ、教育の国際協力の未来において重要な理論的基盤となるものと思料される。
3.未来に開かれた理論的橋梁として
上述の通り『人生地理学』が提起した世界にわたる生命文明地理学の位相と相関における前田教授の「惑星政治学」は、人生地理学という思想を惑星としての地球規模生態系全体へと進展させ、気候正義と生命多様性と共生の理念に接続したと思料される。
この両著作の位相と相関における「倫理的空間の再創造」という視座は、明治と令和をつなぐ理論的橋梁を形成しているとも思料される。牧口先生の世界地理教育理念と、前田教授の惑星的政治学思想は、世界市民的主体を育てる国際教育理念において補完的に活用されうるものと思料されるからである。
本稿の筆者自身も外交官として各国の教育制度や環境保全政策に関与する中で、相関の意味を何度も現場で問い直す経験をしてきた。そこで必要とされるのは、制度設計だけではなく、共感を起点とした地球倫理の理念であり、その点で常に日本と各国間の相関の検討を求められた。そのことにおいて、前田教授が示唆するセンス・オブ・ワンダーの感性は、21世紀外交の基盤とすべきものであり、世界平和のための鍵としての概念ともなり得ると思料される。また筆者は、外務省在任中、「人間の安全保障(Human Security)」という概念の国際的普及に関与してきたが、その経験から鑑みても、前田教授の理念は、以下の点で21世紀国際外交政策実務への示唆に富む。
第一に、「人間の安全保障」は当初から「国家」ではなく「人間」に焦点を当て、健康・教育・環境・政治参加などを含む多元的安全保障を重視してきた。前田教授の惑星的ケアの論点は、この視座をさらに進展させ、「ヒトとノンヒューマンにおける相互依存性」を再構成し、地球自身のプラネタリー・ヘルスに着眼している。
第二に、気候変動やパンデミック対応におけるグローバル・ガバナンスの現場で必要とされる多国間主義の再活性化と市民レベルでの参加拡大こそは、まさに前田教授が示唆されるところの国際政治学の再編に深く通じていると思料するものである。
すなわち、『「人新世」の惑星政治学』は、自然科学と人文学、国際政治思想と世界地理教育理念に加え、前田教授自身による「里山での自然体験型フィールドワーク」の政治学科目実施など理論と実践とを架橋する実行も伴っている傑出の書である。著者前田教授が編み出した「惑星政治学」という言語化は、いま国際政治が直面する制度的・倫理的・文明論的な閉塞を打開する可能性をもつものと思料するものである。
4.エピローグ――生命文明学的相関から惑星政治学的相関への展開
牧口先生の『人生地理学』が前提とするのは、生命文明学的な相関によって考究され、世界地理学の枠を超えた「世界地政学」でもあったとも拝察されないであろうかと思料するものである。これを承継したと思料される前田教授の「惑星政治学」は、惑星的スケールでの相関──すなわち気候、資本、戦争、地球生態系といった巨大な関係性──を前提にした、もう一つの人新世の創出概念であったとも思料される。ある地域の気候、地形、資源は、そこに生きる人々の生活様式や価値観を形成しうる。逆に人間の活動もまたその地域環境を地質の構造から変容(metamorphosis)させる「緩慢な暴力」としての実存であるという地球のいわゆる「人新世」のフェーズに入っていることに前田教授は警鐘を鳴らしている。
この「惑星政治学」と「人生地理学」の二つの深淵な哲理は、位相と相関の動的連関性を中核に据えて共鳴しているのではないかと勤考されるものである。とりわけ、牧口先生が地理教育を自己と環境との関係を深める営みとして哲学されたと思料される視座は、前田教授の人新世の惑星政治学がヒトとノンヒューマンの関係性から生まれるとする国際政治思想の視点と通奏低音(バッソ・コンティヌオ)しているものとも思料する。
5.結語として:123年の射程と「人新世」の惑星政治学の新しい地平
最後に、「人生地理学」において牧口先生が構想されたものは、生命文明と世界地理学の相関の中で意義づけ直す倫理の知的営為であったとも考えられないであろうか。それは、単なる空間的知識ではなく、「倫理の地理学」としての倫理哲理及び教育哲理との統合でもあったとも勤考される。
それから123年、前田教授の『「人新世」の惑星政治学』は、グローバル危機の時代における「新しい生命尊厳の地球地理学=惑星政治学の倫理空間」の構想とも言えないだろうか。その点で、牧口先生のご著作の位相と相関の先にある前田教授の学究は、時代とスケールの隔たりを超えて、「地球地理学と生命文明」「倫理学と国際政治学」を結び直す理論的橋梁とも成り得ると考えられる。
今後の有望な展開として考えられるのは、こうした思想をいかに教育・社会政策・実践運動に組み込むかであると思料される。牧口先生が生涯を賭して教育改革に挑んだように、前田教授の学究もまた、実践的射程を伴うものであると思料するからである。
6.なお、ここに本書の構成を附記させて戴き、紹介の一助となれば幸いと願うものである。
(青土社/2023年6月20日刊/2,860円税込)
《目次》
序章 「人新世」の政治的リアリズム:惑星思考の鍵を握る人智圏と感受性
第I部 「人新世」の惑星政治学
第1章 惑星政治とは何か:人新世時代の脱人間中心主義に向けて
第2章 国際政治学はマテリアル・ターンの真意を受けとめられるか?:多重終焉の黄昏の中で
第3章 領土と主権に関する政治理論上の一考察:暴力、人民、国連をめぐるアポリアに抗して
第4章 石油から見る惑星限界の系譜学:ヒトとモノによる世界秩序
第II部 ノン・ヒューマンと共に生きる:生命の序列化を超えて
第1章 構造的暴力論から「緩慢な暴力」論へ:惑星平和学に向けた時空認識の刷新に向けて
第2章 ノン・ヒューマンとのデモクラシー序説:ヒトの声だけを拾えば済む時代の終焉へ
第3章 脱人間中心のガイア政治:リスクとしての人間とポストSDGsへ
第4章 人新世のアナーキカル・ソサイエティ:ノン・ヒューマンとの戦争論として読み解く「持続可能な開発目標」
第5章 ノン・ヒューマン(と)の平和とは何か:近代法体系の内破と新たな法体系の生成へ
関連記事:
書評『評伝 牧口常三郎』――〝創価教育の父〟の実像に迫る
「創価の父」牧口常三郎(上)――信念の獄死から75年(2019年掲載)
「創価の父」牧口常三郎(下)――世界に広がる実践と評価
連載「創価教育の源流」を学ぶ:
第1回 創価教育学を生み出した牧口常三郎の教育実践[前編]
第2回 創価教育学を生み出した牧口常三郎の教育実践[後編] (第3回以降も随時掲載)