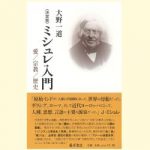宗教の歴史的功罪を見つめる
フランスの歴史家・思想家ジュール・ミシュレ(1798~1874)。世界屈指の研究機関コレージュ・ド・フランスの教授でもあった彼は、数多くの書物を著し、人間の生活文化を視野に収めた総合歴史学を目指す〝アナール学派の源流〟ともいわれる。さらに母国では歴史学の分野を超えた大作家とされ、ユゴーやバルザックと並び称されることもある。
本書は、ミシュレの入門書であるが、生涯の事績を列挙するようなことはせず、大著『人類の聖書』にミシュレが書き残した特徴的な一節を導きの糸に、彼の歴史観の底に流れる問題意識を明らかにする試みである。
インドから(一七)八九年[=大革命]まで光の奔流が流れ下ってくる。「法」と「理性」の大河である。遥かなる古代は君なのだ。君の種族は八九年となる。そして中世はよそ者となる。(『人類の聖書』大野一道訳/藤原書店、本書12ページ)
中世から近代への歩みを踏み出した時代を「ルネサンス時代」と名付けたのはミシュレである。そしてルネサンス時代に始まる近代化を実現したのがフランス革命であった。
同時代の他の歴史家は、フランス革命をカトリック教会と封建制度によって抑え込まれていた初期キリスト教への回帰であり、隣人愛と神の前の平等という理念の実現としてとらえていたようだ。
しかし、ミシュレはフランス革命がもたらした近代化を、キリスト教のみならず、西洋文明の遥か以前から存在するインドをはじめとする東洋の信仰の復興でもあると位置づけた。こうした独自の歴史観はどこから生まれたのか。そもそもミシュレは宗教をどう考えていたのだろうか。
十字軍の遠征やユダヤ人への迫害、異端審問や魔女狩りなど、流血と暴力に満ち溢れた歴史がある。ミシュレは歴史家として、その原因である宗教に対して否定的であった。
また中世以降のキリスト教は壮大なスコラ哲学を生み出したが、その反面、思考の機械化と祈りの機械化を生み出し、死んだ宗教と化したと考えた。さらには硬直化した思考は教条主義へ走り、神という世界と人間を支配する「絶対理念」を信じない者は劣った存在であるとし、殺戮することも辞さない狂信を生み出した。歴史的に考えれば宗教は功よりも多くの罪をなしてきた。ミシュレは人間を隷属させ手段化する宗教や思想に対し徹底的に厳しい評価を下し、その相対化と乗り越えを考えるようになる。
生涯民衆と共に生き、民衆を自負する
成長しているのは誰でしょう? 子供です。渇望しているのは誰でしょう? 女です。熱望し上昇してゆくだろうのは誰でしょう? 民衆です。/そこにこそ未来を探し求めねばなりません。(『学生よ』大野一道訳/藤原書店、本文ママ、本書194ページ)
ミシュレの独自の思索の原点には、彼の出自が大きく関係している。ミシュレは貧しい印刷業者の息子としてパリで生まれた。当時は現代と比較にならないほど高等教育への道は狭き門であった。彼はそうした環境をものともせず、苦学に苦学を重ね、独学で教授資格試験に合格した。
研究職に就いてからも、彼は終生、民衆の出自であることを誇りとしていた。今まで歴史研究の対象とされていなかった「民衆」「女性」「自然」へと目を向けるようになる。当時、民衆や女性は歴史形成の主体ではなく、自然は人間に働きかけられるのみの心無き受動的な存在と考えられていた。そうした偏見を打ち破り、歴史を作る原動力は女性と民衆であり、また人間は自然の一部であり、宇宙それ自体がさまざまな生命によって織りなされる一つの巨大な生命であると確信するに至った
人類の精神革命を予見する
革命は人間の奥底に行き、魂に働きかけ、意思に到達しなければならないのです。革命は欲せられた革命、心の革命、〈道徳的かつ宗教的〉な変革とならなければならないのです。(同、本書199ページ)
愛とは、自己の存在や力を超えようとする生命の努力である(『海』加賀野井秀一訳/藤原書店、本書247ページ)
ミシュレは宇宙に調和をもたらしているのは、外側から宇宙を支配する神のような存在ではなく、宇宙に遍満し、しかも全ての生命に内在する法則性であると考えた。そこから、西洋文明の誕生以前から存在している東洋の宗教への探求を進め、特に古代インドの信仰に注目するようになる。
古代インドに代表される東洋の信仰では絶対神は存在せず、神性は遍く宇宙に存在し万物に内在していると説いている。こうした哲学に触れたミシュレは古代から現代にいたるまでの宗教の底流には、宇宙を支配する「絶対理念」ではなく、生命に調和をもたらす究極の法である「普遍的な愛」が流れていることに気づく。
人類はこの普遍的愛に目覚めることによって、自然を含めた他者に対する傲慢さを克服し、世界において創造的な力を発揮することも可能になる。こうした人間の精神革命が先行してこそ、人間の尊厳というフランス革命が掲げた理想も初めて現実のものとなる。その未来に向けての展望が、『人類の聖書』にある言葉の真意ではないだろうか、と著者は述べている。
ミシュレの没後から約150年が経過した。だが彼が思い描いたような未来はいまだに到来していない。彼が共感を寄せた東洋の宗教も一神教の宗教と同じように紛争の原因となっている。わが国でも戦前・戦中の国家神道は宗教統制を行い、アジアの民衆には過酷な植民地支配、日本の民衆には亡国の不幸を招いた。自然と人間の共生という課題もいまだに解決されてはいない。
しかし、そうした状況であるからこそ、もう一度ミシュレの精神に立ち返る必要があるのではないか。彼が歴史と格闘する中で見出した宇宙的秩序感覚にもとづくヒューマニズムと精神の革命という思想こそ、ミシュレが後世に遺した大いなる遺産であろう。現代人は彼の遺産に学ばなければならない。歴史とは復活であるという意味の言葉をミシュレは残している。全ての社会変革に先行する精神革命――、彼が予見した困難な課題に挑むときミシュレは私たちの心の中に蘇るに違いない。
『〈決定版〉ミシュレ入門〔愛/宗教/歴史〕』
(大野一道著/藤原書店/2024年10月30日)
関連記事:
「小林芳雄」記事一覧